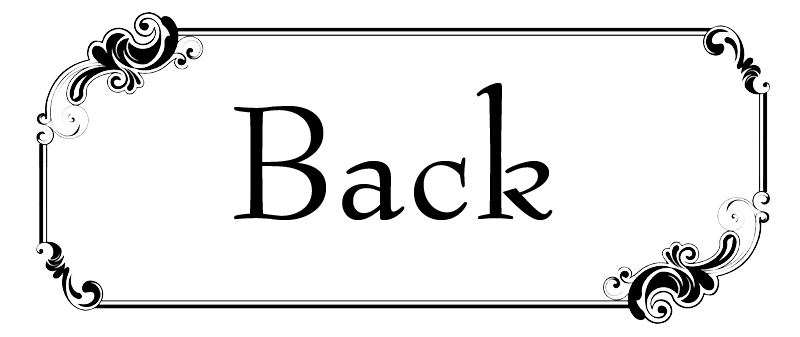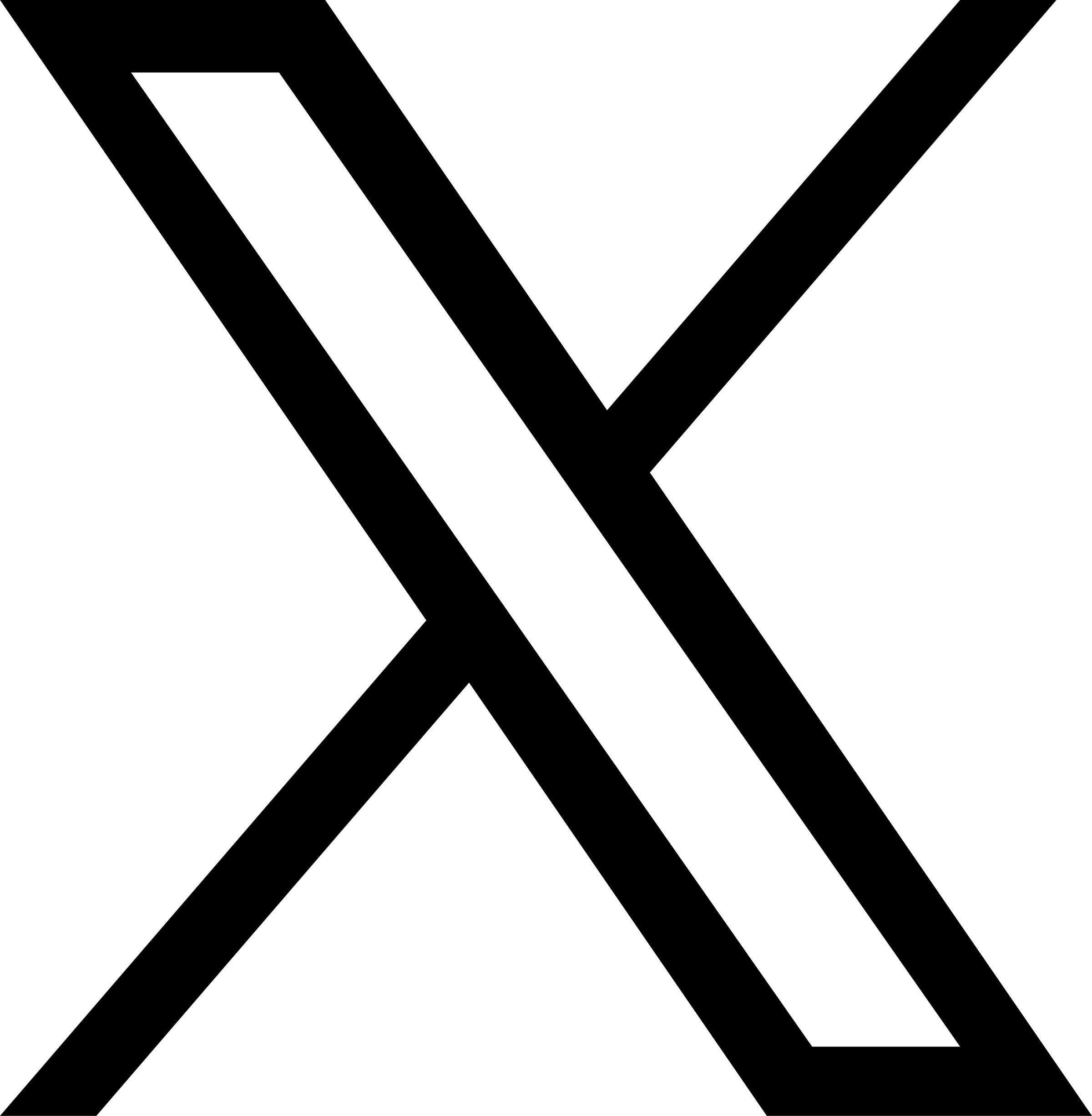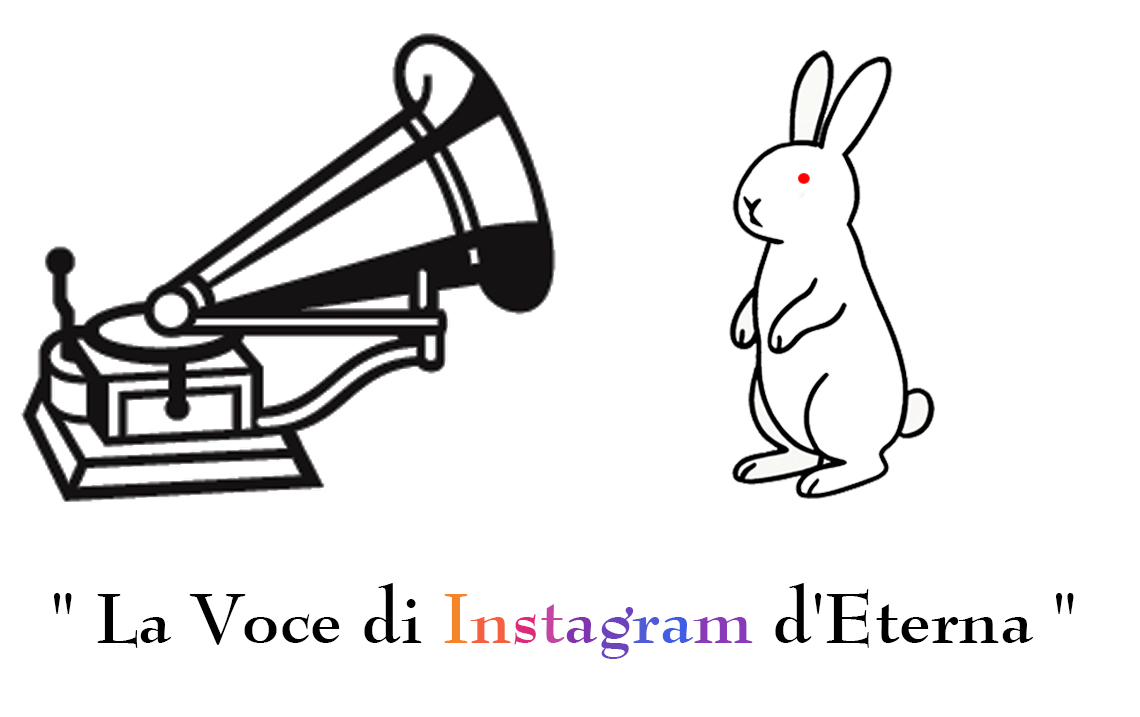「はじめに」
記 エテルナトレーディング
このコンテンツは2008年のARSCジャーナルに掲載された、
トーマス・ファイン氏の論文『商用デジタル録音の夜明け』を
WEB上で見やすい様に編集を加えた日本語版となります。
ARSC(The Association for Recorded Sound Collections)は、
原型的な民族音楽など商業的には価値が薄い録音が、
公共機関の主導では散逸してしまうという危機感を感じた、
図書館員や音楽関係者によって発足したアメリカの非営利法人です。
とにかくライブラリ化に心血を注いでいるのが特徴で、
その特性上、レコード・コレクターも会員として重要な役割を担っています。
録音の実物が確認できて初めて真実が判明する点は、
弊社との共通点も多分に有るのではと思います。
ARSCは発行した機関誌に掲載許可したオーディオ史にとって重要な論文は、
著作者の権利や功績を侵害しない限りは遍く周知されるべき、
という運営方針を取っています。
ARSCポリシーページへ
弊社は著作者トーマス・ファイン氏と、
掲載誌ARSCジャーナルの権利と功績をここに明確に記すと共に、
本コンテンツがライブラリ目的であり、
直接的な金銭の授受を目的としたものでない事を宣言いたします。
一読していただければ御理解を得られると信じますが、
この論文にはオーディオ史において日本の技術者が果たした歴史的役割について、
非常に重要な事実が記されています。
音楽技術者を志す若者を含めた、
音楽を愛する日本人に須らく知っていただきたい内容が記されているのです。
この点においてARSCの基本ポリシーを侵害しないと愚考した結果、
本コンテンツの製作に至ったものであります。
オリジナル英文PDFに掲載されている写真については、
本邦での権利確認が困難となるため割愛しましたが、
オリジナル英文PDFは無料のライブラリとして、
いつでも閲覧/入手が可能となっております。
論文のオリジナルを確認する
WEB上に保存されたコンテンツの重要性は、
実生活における公共施設である図書館と同様に、
閲覧数、アクセス数が指標となります。
本コンテンツの内容に趣きを感じた際には、
オリジナル英文PDFも是非ご確認ください。
気紛れで構わない一つのクリックが、
オーディオ史を保存しようと志す有志達の一助に繋がります。
最後に改めて。
著作者であるトーマス・ファイン氏と、
掲載とWEB公開を行ったARSCジャーナルに、
思い付く限りの最大の謝辞を。
「The Dawn of Commercial Digital Recording」
by Thomas Fine
「商用デジタル録音の夜明け」
トーマス・ファイン
商用デジタル録音が広く普及してから30年ほどしか経っていませんが、
多くの「神話」や「初」に関する主張が生まれてきました。
この文章は当時の関係者の証言を集め、
初期の商用デジタル録音で行われてきた画期的な事例を
出来る限り真実に沿う形でまとめたものです。
音声の送信と録音のためのデジタルパルス符号変調(PCM)は
1930年代のアメリカで電話通信技術の向上を目的に開発されましたが、
音楽にデジタル録音を持ち込み商業的にリリースした最初の企業は
日本のデノン(DENON)社でした。
1989年5月のオーディオ・エンジニアリング・ソサエティ(AES)会議で、
デノンのエンジニアが初期のデジタル録音の体験談を語ってくれました。
彼の主張では親会社である日本コロムビアがデノンの機器を使用して
『1977年末』に行ったのが「アメリカ初の商用デジタル録音」となります。
一方、米国内には様々な「デジタル初録音」を主張する人がいます。
サウンドストリーム・デジタル・システムは1976年から
様々な場所でテスト使用されていました。
しかし実際の商用リリース音源として使用されたのは
Soundstreamが第2世代に改良された後の『1978年』でした。
これは米国初の交響曲デジタル録音として広く知られています。
ほとんど同時期にミネソタ州の音楽スタジオでは、
3M(スリーエム)社のプロトタイプがテスト稼働していました。
並行して録ったアナログ録音と比べて音響的に優れていると判断された、
このデジタル音源の室内楽LPはデジタル録音で初となるグラミー賞を受賞しました。
ヨーロッパではDECCAレコードのエンジニアが、
同社の技術開発室で独自のデジタル録音システムを設計し、
1979年のウィーン・ニューイヤーコンサートで初公開しました。
これはヨーロッパの大手レコード会社によって行われた、
最初の商用デジタル録音でした。
本稿で紹介する録音はデジタル時代への最初の一歩であり、
それまでの音楽ビジネスを構築したアナログ技術から巣立つ最初の一歩でした。
著者は手に入る限りのオリジナル盤、オリジナル資料を集め、
可能な限り実際の関係者にインタビューしました。
1980年代の初めまでに大手レコード会社は何らかの形でデジタル録音を採用しました。
アナログ録音はマルチトラック録音の分野では重要な役割を担っていましたが、
それもデジタル録音がすぐに取って代わる様になっていきました。
そして何より、1980年代初頭におけるデジタル技術の果たした大きな役割は、
消費者に向けて新しい録音メディアをもたらしたことでした。
フィリップスとソニーは1982年にCDを発売、
1980年代の終わりまでにLPを超える売り上げを記録しました。
その後すぐにカセットテープの売り上げも追い越し、
1990年代以降はCDというメディアが北米、ヨーロッパ、
そして日本の音楽市場を独占したのです。
デジタル録音の進化によりアナログ録音は少数の熱心な人々の領域となり、
コンパクト・ディスクが全てのアナログ・メディアに取って代わりました。
しかし、そのコンパクト・ディスクも現在は終焉を迎えており、
今後はインターネット配信が主要メディアになる運命にあると思われます。
『真夜中』
デジタルパルス符号変調(PCM)は1930年代に米国のベル研究所で発明されて、
最初は電話音声のための技術として利用されました。
第二次大戦中、ロンドンとアメリカ国防総省を繋いでいた
非デジタルの軍用回線がドイツ軍によりセキュリティを突破されます。
この事態にベル研究所のエンジニアは「SIGSALY」と呼ばれるPCM暗号システムを開発。
1943年に導入されると最終的に12台の「SIGSALY」が製造され、
西側世界で運用されましたが1946年には廃止されます。
このデジタル暗号化システムに関する特許は1976年まで機密扱いでした。
「SIGSALY」は世界初となるデジタル量子化された音声の送受信を実現させたのです。
ここから、次の話は1960年代の日本、NHKの技術研究所に飛びます。
NHKのエンジニアは1967年にモノラルPCMオーディオレコーダーを開発、
1969年までには実用的な2チャンネルステレオのPCMレコーダーを完成させました。
NHKのシステムは32kHzのサンプリングレートと13ビットの解像度を持ち、
産業用ヘリカルスキャン・ビデオテープを記憶媒体として使用しました。
このPCMオーディオ情報をVTR信号に変換するという概念は、
1990年代まで使用され続けました。
初期のCDの多くはU-Maticの3/4インチVTRをベースにしたSony1600~1630システムと、
民生用にも販売されたデジタル録音デバイスを使用してマスタリングされており、
Sony PCM-F1(1981年発売)などPCM音声をVTRに録音する機材が活用されました。
同じ頃、英国BBCはテレビ放送の音質を向上させるためにPCMの実験を行っています。
BBC研究部門は1970年代初頭に2チャンネルPCMレコーダーを開発、
1972年に導入されたこのシステムは、音声が放送センターでデジタルに変換され、
送信した先でアナログに戻されるという13チャンネルのPCMシステム。
1980年代初頭まで使用されていました。
この技術の一部は後にアメリカの3M社にライセンス供与され、
3M社は1977年末にデジタル・マスタリングシステムを発表します。
米国ではアメリカ公共放送(PBS)とデジタル・コミュニケーションズ社が提携し、
1973年にデジタル通信システムを発表しました。
映像信号とPCMオーディオ信号を共通の回線で送信し、
最大4つのオーディオ信号を単一のデジタル情報として活用できる
DATE(Digital Audio for Television)システムと呼ばれるものです。
『夜明け前』
日本コロムビアは日本国外ではデノン(DENON)として知られ、
大手レコード会社であると同時に音楽機器メーカーでもありました。
デノンはダイレクト・カッティング技術の復刻の先駆者でしたが、
1960年代後半からLPの音質を改善する研究を行っており、
アナログ・テープ特有の音の歪みを解消する方法を模索していました。
最終的にデノンのエンジニアは技術的に先駆者だったNHKの研究所を訪問し、
共同開発の契約を取り付けました。
目的は「磁気テープ特有の弱点を克服した録音を作成すること」です。
『デジタル録音の夜明け』
NHKからの技術協力を取り付けたデノンは1969年から1971年にかけて、
ステレオPCMレコーダーを借り受けて数多くのテスト録音を実施しました。
当時のデノンのエンジニアだった穴沢武明によると、
「このテスト録音からはシステムの改善について多くのアイデアを得ました。
そしてPCMデジタル技術を初めて使った2枚のLPが生まれたのです。
初期のデノン/NHK録音で作られた世界初の商用デジタル録音は、
日本コロムビアから1971年1月にリリースされた、
スティーブ・マーカス『サムシング』NCB-7003と
ツトム・ヤマシタ『ツトム・ヤマシタの世界』NCC-8004です」
PCMデジタルがアナログ・テープよりも優れていると判断したデノンは、
VTRベースの独自システムの開発に着手しました。
彼らの目標はオーディオ品質とマルチトラック録音機能の向上にありました。
1972年にデノンは13ビット解像度と47.25kHzのサンプリングレートを特徴とする
8チャンネルシステムであるDN-023Rを発表。
記録媒体として日立製作所(当時は芝電子)の産業用VTRテープを採用した
この新しいシステムは1970年代のほとんどの商用録音で使用されました。
穴沢氏曰く、
「記録にはVTRのモノクロ・モードを使用しました。
カラー・モードよりもテープ切れに強くてコストも低かったので。
DN-023Rに搭載した高精度なヘッドのお陰で、
より自由に録音を編集し、LPをカッティングすることができました。」
このシステムで作られた最初のLPは日本コロムビアNCC-8501、
スメタナ四重奏団によるモーツァルト:弦楽四重奏曲K.458とK.421でした。
1972年4月24日から26日にかけて東京の青山タワーで録音され、
1972年10月にリリースされました。
この1972年10月のシーズンにはクラシック、ジャズ、日本の伝統音楽など、
少なくとも6枚のデジタル録音LPがリリースされました。
また、1974年12月2日と3日にはフランス中北部のノートルダム・ド・ローズ教会まで赴き、
パイヤール室内管弦楽団によるバッハ「音楽の捧げ物」を録音。
この欧州初となった商用デジタル録音は1975年5月にLPでリリースされました。
1977年には出張レコーディング向けに小型改良したDN-034Rを開発。
穴沢氏によると47.25kHzの8チャンネルシステムは旧機種と同一でしたが、
「エンファシス付き14ビット(15.5ビット相当)」を使用することで
DN-023Rに比べて解像度を向上させたとのことです。
また、ポピュラー音楽に不可欠なオーバー・ダビング機能も実装しています。
驚くべきことに、47.25kHz/15.5ビット相当という解像度は、
後にデジタルオーディオテープ(DAT)規格で採用される
48kHz/16ビットと殆ど同じ水準なのです。
1977年11月、日本コロムビアのプロデューサー小沢義雄は、
穴沢氏と山本薫というもう一人のエンジニアと共に
DN-034Rをニューヨーク市のサウンド・アイデア・スタジオに持ち込み、
ジム・マッカーディのエンジニアリングでジャズのデジタル録音を行います。
このアーチー・シェップ「オン・グリーン・ドルフィン・ストリート」は、
1977年11月28日に録音され1978年5月に日本コロムビア YX-7524として発売。
これは米国で最初に発売された商用デジタル録音でした。
また、このNYでの録音セッションから生まれた最初の日本盤は、
フランク・フォスター・ビッグバンドの「マンハッタン・フィーバー」でした。
(YX-7521、1977年11月29~30日録音、1978年4月リリース)。
上記の2枚を含めた合計7枚のジャズアルバムが
1977年の11月と12月にDN-034Rを使用して録音されました。
1982年にコンパクトディスクがデビューするまでの期間に、
デノンは400を超えるLP用デジタル録音を保管庫に収めたのです。
『サウンド・ストリーム』
PCMの発祥の地であるアメリカでも、
複数の企業のエンジニアが1970年代のデジタル録音の技術開発に邁進していました。
先頭に立ったのはユタ大学教授のトーマス・ストックハム博士。
ストックハムはハネウェル社の高品質なレコーダーを使用した
デジタルオーディオ録音/編集システムを開発しました。
このシステムはコンピュータを使用して音楽波形の視覚的な編集を可能にし、
現代のデジタル・オーディオ・ワークステーションの先駆けとなりました。
また、ストックハムはデジタル信号処理の先駆者でもあり、
20世紀初頭にエンリコ・カルーソーの録音にも使用された
録音時の歪みを解消するプログラムを作成しています。
1976年までにストックハムはサウンドストリーム社と、
37.5kHzのサンプリングレートで16ビットの解像度が可能なレコーダーを開発。
A/DおよびD/A変換回路、メータリング/レベルコントロールなどを搭載し、
ハネウェル社のレコーダーに対してデジタル信号の入出力を可能にしました。
さあ、現場に出て音楽を録音する時が来ました。
1976年の夏のシーズンにサンタフェ・オペラ団は
現代オペラ『The Mother of Us All』を上演しました。
ニュー・ワールド・レコーズはロックフェラー財団の助成を受けて録音を決定。
これこそストックハムが1994年のオーディオ誌のインタビューで
「最初のテスト録音」と語ったものです。
実際のLPにはアナログ音源が使われましたが、
現場にはプロトタイプのサウンドストリーム・レコーダーが用意されていました。
レコーディング・エンジニアを担当したジェリー・ブルックの証言を紹介します。
「実際の録音の前にストックハムが私に連絡してきて、
サウンドストリームと通常のレコーダーと並行して録音可能か尋ねました。
そこで私たちは協力して録音コンソールからの信号を
サウンドストリームにも並行して送るシステムを作りました。
実際に録音を始めてみるとストックハムがインターフォンをかけてきて、
ハム音が入っていることを伝えてきました。
驚いて音量を上げて確認しましたが、私には何の異常も聞こえません。
そこでインターフォンをかけ直すと-80dBくらいのハム音だと伝えてきたのです。
当時、最高のノイズ低減システムは-70dBまでの対応でした。
-80dBはテープ再生時のバックグラウンド・ノイズに埋もれる程度のものです。
当時のサウンドストリーム・レコーダーには2トラックしかなかったですが、
ストックハムは2つの録音の比較から多くのことを学べると満足していました。
私にはデジタル録音の細部まで理解する事は出来ませんでしたが、
何か今までと違う技術を扱っている感覚を持ちました。
明らかに未来の記録媒体である、という忘れられない印象が残ったのです。」
ストックハムはこのテストで「すべてが完璧に機能した」と語り、
1976年秋のオーディオ・エンジニアリング・ソサエティ(AES)会議で
実機のデモンストレーションを行いました。
このデモンストレーションは録音エンジニアのバート・ホワイトの注目を集めます。
1977年8月にホワイトはカリフォルニアのガーデン・グローブ・コミュニティ教会で
ヴァージル・フォックスのソロ・オルガン録音を企画。
Crystal Clearレーベルのマスタリングエンジニアの筆頭である、
スタン・リッカーが旋盤を担当し、
ダイレクト・カッティングで収録予定でした。
この時にサウンドストリームに並行した音声を送りテスト録音を作成したのです。
依然として16ビット/37.5kHzサンプリングレート、2チャンネル仕様ではありましたが。
このセッションを巡っては幾つかの論争があります。
スタン・リッカーによれば1977年の録音がアナログ録音であることは疑いの余地なく、
サウンドストリームはバックアップとしての使用だったと主張します。
しかしサウンドストリームの録音は最終的にUltraGrooveレーベルから
1981年に「The Digital Fox」という題名でLPリリースされ、
「米国初のデジタル録音」という見出しが付きました。
バート・ホワイトはストックハムのデジタル音源を使用しており、
1977年のCrystal Clear盤とは演奏も音質も全く違うと主張します。
ストックハムは1994年のインタビューで、
「私たちはCrystal Clearレーベルに赴いてフォックスのレコーディングを行った。
この録音は非常に興味深いもので、ここから経営が軌道に乗り始めた」と語る。
関係者の発言が正しいならば、
デジタル録音とアナログ録音の2チームが同時に雇われていたのでしょう。
考えられるシナリオとしては重要なテイクでダイレクト・カッティングに失敗した場合、
あるいは大ヒットとなって途方もなく売れた場合に備えて、
音源の保険としてサウンドストリームを採用したというものです。
いずれにせよ、この1981年のLPは米国最初の商用クラシック録音ではありません。
その栄誉は当時オハイオ州クリーブランドに本拠を置いていた、
小さなクラシックレーベルだったTelarc社に帰属します。
Telarcの創設者であるジャック・レナーとロバート・ウッズは、
1977年11月にNYでサウンドストリームと出会い大いに感銘を受けましたが、
実際の録音に際してプロトタイプに備わる20Hz~15kHzの周波数対応から、
20Hz~20kHzに対応できるようにサンプリングレートを拡張するよう依頼しました。
レナーはステレオ・フィル誌のインタビューで次のように回想します。
「我々は当時ダイレクト・カッティングで2枚のLPを作ったところでした。
NYでのデモンストレーションを聞いて興味を持ち、
ストックハムに改良を直接お願いしたのです。」
改良を要請した理由は、高域があまりにも限られていると感じたから。
私たちは、もっと倍音や空気を聴きたかったのです。
これはプロトタイプには欠けていた部分でした。」
驚くことにストックハムはこの小さなレーベルの依頼を受けることにし、
1978年1月下旬には50kHzサンプリングレート/4トラック仕様にシステムを改良し
Telarcが希望するクオリティの録音準備が出来たことをレナーに通知しました。
この初めてのデジタル・レコーディングのために、
Telarcは伝説的な指揮者であるフレッド・フェネルと契約を結んだが、
理由は地元クリーブランドの出身で頼みやすかったから、とレナーは語ります。
フェネルはホルスト「2つの組曲Op.28」と
ヘンデル「王宮の花火」、そしてバッハの「幻想曲ト長調」を選曲。
録音は1978年4月4日から5日にかけてクリーブランドのセブランスホールで行われました。
録音後すぐにリリースされたこのLPは批評家の称賛を受け、
多くの主流メディアで取り上げられました。
ワールドブック百科事典ではこの米国初のデジタル録音を
ホルストでの大音量の大太鼓にちなんで「世界中に響く大太鼓」と表現しました。
マスタリングを担当したリッカー氏も
「信じられないほどダイナミックで…大太鼓の処理には苦戦した」と語っています。
レナー自身は次のように回想しています。
「編集はソルトレークのサウンドストリーム本社で行いましたが、
コンピュータ編集システムはかなり洗練されている印象でした。
試聴会で再生した時のフェネルの反応は単純で『ワオ!』...これだけ。
この試聴会には主要なオーディオ雑誌のライターが大勢で見学に来ていたのですが、
全員がデジタル録音の凄さを目の当たりにして驚いていましたね。」
ただし、レナーは1978年に行われた他の2つの録音こそが、
「米国初の商用デジタル録音」だと考えています。
「商用デジタル録音として米国で初めて発売されたオーケストラ録音」
ロバート・ショウ指揮アトランタso./ストラヴィンスキー&ボロディン
Telarc80039 1978年6月録音。
「商用デジタル録音として米国で初めて発売された世界的オーケストラ録音」
ロリン・マゼール指揮クリーブランドo./ムソルグスキー&コルサコフ
Telarc80042 1978年10月録音
Telarcが行ったサウンドストリーム録音の一部はSACDとして再版しています。
デジタル音源をアナログ再生し独自のA/Dコンバーターを使用して製作しているとのこと。
リマスタリングを担当したポール・ブレイクモアは
数多くの比較を行い「デジタル-アナログ-デジタル」の形に辿り着いたと語ります。
「一度アナログを経由するとデジタル編集単独では感じられない、
微妙なステレオの深さ、ピッチの明瞭さ、そしてサウンドの良さがある。
何故このようなことが起こるのかは分かりませんが、
高品質の再生システムで聞けば違いが判る筈です。」
『3Mシステムとグラミー賞』
ストックハムがサウンドストリーム・システムを完成させていた頃、
ミネソタ州ミネアポリスにある巨大企業3M(スリーエム)は、
独自のデジタル・レコーダーをテストしていました。
英BBCから技術をライセンス供与されて設計された3M社のシステムは、
1977年11月にニューヨークで開催されたAES会議でプロトタイプが初めて披露されました。
3M社が重視したのはポピュラー音楽に必須の多重録音に対応した、
高品質なマルチトラック録音機能でした。
毎秒45インチで移動する特別な配合の1インチ幅のテープを使用した、
50kHz/16bitの解像度と高品位なオーバーダビングや編集機能を兼ね備える
32トラックのレコーダーの完成を目指したのです
1978年に3M社はミネアポリスにあるSound80スタジオに
当時はまだ2トラック仕様だったプロトタイプのレコーダーを設置しました。
スタジオの共同オーナーだったハーブ・ピルホーファー氏にちなんで
「ハービー」というあだ名が付けられていたそうです。
初の商用録音は1978年の6月に行われ、
演奏はデニス・ラッセル・デイヴィス指揮のセントポール室内o.が担当。
曲はコープランド「アパラチアの春」とアイヴス「Three Places in New England」でした。
セントポール室内o.のビル・マクラフリンはこのように回想しています。
「Sound80ではダイレクト・カッティング録音を何度も行っており、
このセッションでも同様だと思っていたのですが、
ギリギリになって3M社が新機材を持ってきて並行しての録音を頼まれました。
たしか3テイクずつ録音をした筈です。
コープランドでは演奏がイマイチなテイクが1つあり、
ほか2つはダイレクト・カッティング時に技術的な問題が起きました。
最初はこの窮地を救うために『ハービー』に頼ることになったのですが、
最終的にはサウンド自体が好ましく感じる様になりました。」
この録音ではダイレクト・カッティングの録音哲学と、
3M社が産んだ新しいデジタル録音技術のユニークな組み合わせが実現しました。
デジタル録音も編集の無いダイレクト録音となっており、
曲間も含めて「リアルタイム」で再生されます。
一方、Sound80レーベルのプレスリリースでは少し表現が違います。
「ダイレクト・カッティングのバックアップとしてプロトタイプを実験的に使用したが、
マスターを聴き比べた結果、デジタル録音の方が優れていると判断しました。」
いずれにせよ、この録音は1979年の室内楽部門でグラミー賞を受賞し、
グラミーを受賞した最初の商用デジタル録音となりました。
3M社のシステムは改良を経て市場に投入され、
複数のスタジオがオールデジタルでのマルチトラック録音を行うようになりました。
ちなみにポピュラー音楽で最初にオールデジタル/マルチトラックで録音されたアルバムは、
1979年にワーナーブラザーズからリリースされた、
ライ・クーダーの「Bop Til You Drop」でした。
『デッカ・デジタルシステムと、
ウィーン・ニューイヤーコンサート』
アメリカの大手音楽レーベルと同様にヨーロッパの大手音楽レーベルも
1970年代後半までデジタル録音についての検討を進めていたそうですが、
実際には積極的に取り組んでいませんでした。
デノンが1974年からヨーロッパでデジタル録音を行っていたにも関わらずです。
デジタル録音への最初の一歩を踏み出したのは英国のDeccaレーベルでした。
オーディオにおける技術開発の長い歴史を持つレーベルです。
デッカの技術者トニー・グリフィスは
1980年2月のオーディオ・エンジニアリング・ソサエティ(AES)会議で、
「デッカ社は1977年以前の時点で試験的なデジタル録音の開始と、
デジタル録音のライブラリ構築を開始すべきと確信していた」と報告しました。
実際、1977年11月のAES会議に登壇したデッカの関係者は、
「満足できるデジタル録音システムが当分は入手できないことは明らかなので、
私たちは自社システムの開発に取り組んでいます」と発言していました。
1978年になるとデッカは緊急課題としてデジタル録音技術の開発に取り組み、
IVCヘリカルスキャン・テープを使用するDecca独自のシステムを考案しました。
このシステムは48kHz/18ビットの解像度を特徴としており、
コンピュータでの編集も可能にするものでした。
このデッカのシステムは2トラック仕様だったのですが、
AES会議ではグリフィスが次のように説明しています。
「我々はマルチトラック対応への必要性を感じていませんでした。
デッカのクラシック録音は2トラック・ステレオが伝統であり、
マルチトラックの空いたトラックはバックアップに使っていたのです。」
1978年の夏から秋にかけてテスト録音を行った後、
ボスコフスキーが指揮するウィーン・フィルの1979年ニューイヤー・コンサートで
自社オリジナルのデジタル録音システムの完成を公開しました。
この2枚組LP(Decca D147D2)が、ヨーロッパ初の商用デジタル録音となりました。
この録音は1996年にグラモフォン(DGG)がCD復刻しますが、
「歴史的な重要性が非常に高い録音」と記載されました。
デッカのデジタル録音システムは改良が重ねられ90年代でも現役でしたが、
1997年に親会社ポリグラムが技術開発室の閉鎖を決定。
60年に渡ったデッカの設計エンジニアリングと革新の歴史に終止符が打たれました。
また、ニューイヤーコンサートの後を追うように、
オランダのフィリップス社もネヴィル・マリナーとのデジタル録音を敢行。
ヘンデルの「6つの合奏協奏曲Op.3」(LP 6514114)を製作しました。
この際にはSony1600/2チャンネルPCMシステムが使用されています。
『エテルナトレーディングからの追記』
ここで述べられているトニー・グリフィス氏の
「DECCAは2トラック・ステレオが伝統」という発言には注意を要する。
実はDECCAには『Phase 4 Stereo』という、
マルチトラックのシリーズが1961年から存在するからである。
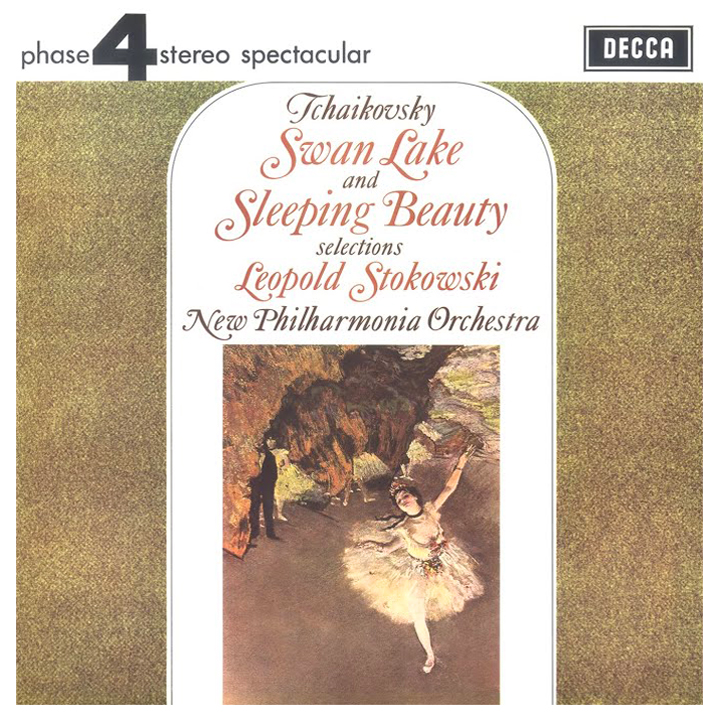
10チャンネルのミキサーから4トラックのテープに録音し、
最終的に2トラックのステレオにマスタリングするという方式は、
当然ながら当時の最先端をいく技術で、DECCAにしか成し得ないものだった。
このシリーズにおいては指揮者が限定されており、
意外なところではシャルル・ミュンシュが起用されているが、
メインとなったのはレオポルド・ストコフスキー。
アニメ映画『ファンタジア』への出演やオーケストラの配置の刷新など、
新技術に対して積極的だった人物が船頭役として採用された。
この矛盾する事実に関しては恐らく『部署』が違ったものと推測される。
FFSS(FULL FREQUENCY STEREOPHONIC SOUND)= SXL番号として知られる、
DECCAのメイン部署にグリフィス氏が所属していたため、
新技術を実験する部署とは交流が殆ど無かったのではないだろうか。
いずれにせよ、この論文からは、
録音技術に関してDECCAが欧州の最先端だったことが窺える。
・世界初の商用デジタル録音(ジャズ)
スティーブ・マーカス&稲垣次郎&ソウル・メディア「サムシング」
番号:日本コロムビア NCB-7003
録音:1970年9月/東京
機材:デノン試作システム
・世界初の商用デジタル録音によるクラシック作品
スメタナ四重奏団 / モーツァルト:弦楽四重奏曲第17番K.458「狩」
番号:日本コロムビア NCC-8501
録音:1972年4月24-26日/東京青山タワー
機材:デノン DN-023R
・西ヨーロッパ初の商用デジタル録音
パイヤール室内管弦楽団 / バッハ:音楽の捧げもの
番号:日本デノン OX-7021
録音:1974年12月2-3日 フランス・セーヌエマルヌ県ノートルダム・ド・ローズ教会
機材:デノン DN-023R
・アメリカ初の商用デジタル録音(ジャズ)
アーチー・シェップ「オン・グリーン・ドルフィン・ストリート」
番号:日本デノン MJ-7262
録音:1977年11月28日 NYサウンド・イデア・スタジオ
機材:デノン DN-034
・アメリカ初の商用デジタル録音によるクラシック作品
フレデリック・フェネル指揮クリーブランド・シンフォニック・ウィンズ/
ホルスト:2つの組曲Op.28, ヘンデル:王宮の花火のための音楽, バッハ:幻想曲ト長調
番号:Telarc 5038
録音:1978年4月4-5日 オハイオ州クリーブランド・セヴェランス・ホール
機材:サウンドストリーム
・初めてグラミー賞を獲得した商用デジタル録音
デニス・ラッセル・デイヴィス指揮セントポール室内管弦楽団 /
コープランド:アパラチアの春, アイヴズ:ニューイングランドの3つの場所
番号:Sound80 DLR-101
録音:1978年6月 ミネソタ州ミネアポリス Sound80スタジオ
機材:3Mプロトタイプ・システム)1979年グラミー賞最優秀室内楽アルバム賞受賞。
・欧州レーベル初の商用デジタル録音によるクラシック作品
ウィリー・ボスコフスキー指揮ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 /
1979年ニューイヤーコンサート
番号:デッカ D147D2 / ロンドン LDR-100012
録音:1979年1月1日 ウィーン楽友協会ホール
機材:デッカ・システム