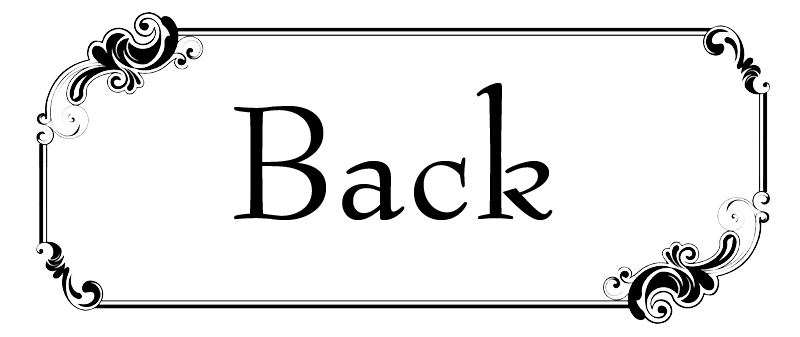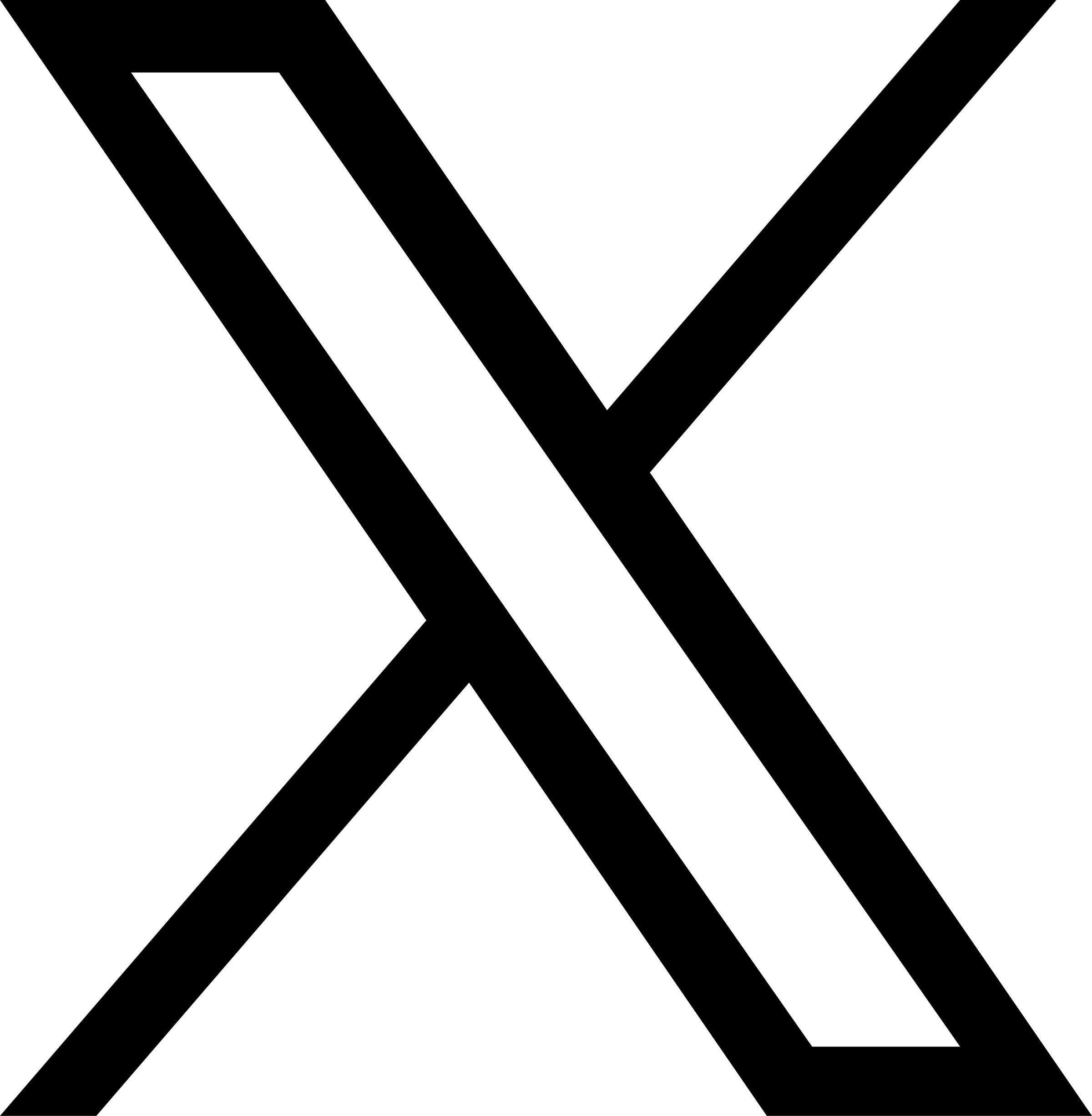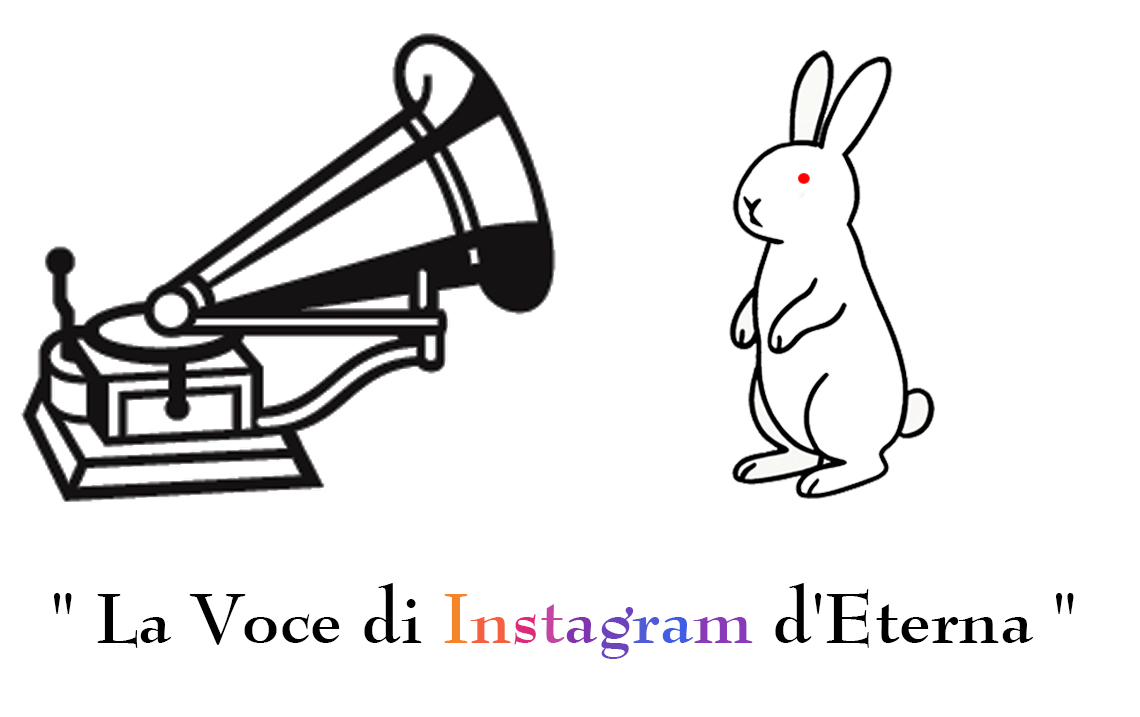当ページでは商品解説の際に経歴説明が重複していたり、
あるいは煩雑になってしまう人物について、
主に『出身言語の資料』を基にして解説いたします。
下記の項目の中から、
調べたい人物名をクリックしてください。
Franz Konwitschny (1901-1962)
【主な活動レーベル】
ETERNA
【経歴について】
現チェコ共和国の東部、モラヴィア生まれ。
元々はヴァイオリン専攻でライプツィヒ音楽院に在学していて、
フルトヴェングラー時代のライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団で
ヴィオラ奏者として音楽活動を開始した。
同楽団での偉大な指揮者との出会いが演奏者からの転向を選ばせたのか、
1927年のシュトゥットガルト国立歌劇場の練習指揮者を経て、
1930年には同歌劇場の首席指揮者に就任。
そして時を経て、運命の1949年が訪れる。
遂に、ゲヴァントハウス管弦楽団に常任指揮者として舞い戻ったのである。
ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団は、
250年を超える歴史を持つ世界初の平民階級オーケストラである。
楽長/常任指揮者は『ゲヴァントハウス・カペルマイスター』と尊称され、
歴代のカペルマイスターにはフェリークス・メンデルスゾーン、
アルトゥール・ニキシュ、ヴィルヘルム・フルトヴェングラーらが名を連ねる。
コンヴィチュニーは第二次大戦でボロボロになった同楽団の復興に尽力するなど
没年の1962年までカペルマイスターの職を全うし、
ゲヴァントハウス管弦楽団を世界有数の優れた管弦楽団に育てあげた。
同楽団と東独ETERNA レーベルを語る上で
コンヴィチュニーが絶対に名前を外せない人物なのは間違いないが、
やはり特筆すべき業績は1958年から1961年にかけてライプツィヒで録音された、
世界に誇るベートーヴェンの交響曲全集だろう。
「聴けば判る」と言えるほどの名録音で幾度もプレスされたが、
東側ではステレオ・レコードの発売開始が西側より10年近く遅れたため、
プレスの変遷と相まって判別が困難になってしまった。
超高音質を誇りETERNAの顔とも言えるV字ステレオ盤、
日本では人気が低いため安価だが圧倒的な音質を持つモノラル盤、
再プレス時のレーベル違いにジャケット違いetc...
屋号を見ていただければお分かりいただけると思うが、
弊社エテルナトレーディングは全容を解明している。
音質と予算とのバランスを考慮した提案が可能なので、
いつでも御相談いただきたい。
【演奏スタイル/特徴】
コンヴィチュニーほど聴き手に媚びない指揮者も珍しい。
聴衆がいてもいなくても関係なしといった風情の、
虚飾が一切ないスタイルである。
フルトヴェングラー好きが聴けば、最初は地味な印象を受けるだろう。
無駄な音を出さず、必要最小限の中で最大限の表現を産み出すからだ。
むしろ表現を『しない』指揮者というべきか。
贅肉がそぎ落とされた引き締まった演奏、とでも書けば簡単だが、
しかし実に味わいが深い。
そして、機を見れば脇目も振らず直線的に猪突猛進と言える程に突進していく。
ブルトーザーの如く全てをなぎ倒して激震する怒涛の演奏に繋がっていくのである。
周りや後ろを振り返らず、前だけを見据えてマイペースで突き進む。
この無作為こそがコンヴィチュニーの特徴で、
このぶっきらぼうな渋い音でソッポを向かれると、とことん追いかけたくなる。
ところがいくら追いかけても後姿しか見せないのがコンヴィチュニー。
いつ聴いても全てを見ることができない、だから何度でも聴くことができる。
この奥深さこそが彼の最大の美点なのである。
余談だが「コンヴィチュニー」は無類の酒好きで、
仲間には「コンウィスキー」と揶揄(あだ名)されていた。
逆に言えば、それほど親しく深い絆で結ばれていたからこそ、
機関車が煙を上げて突き進む様な、一丸となった演奏が可能だったのだろう。
コンヴィチュニーの在庫を見る
Karl Ristenpart(1900-1967)
【主な活動レーベル】
Les Discophiles Français
Le Club Français Du Disque
【経歴について】
ドイツ北部の街、キールの生まれ。
1930年代からベルリンで指揮者として活動していたが1953年に同地を離れ
ドイツ南西部、フランスとの国境を有するザールブリュッケンに転居する。
転居した1953年の10月からザール室内管弦楽団を自ら創設し活動を開始。
メンバー18人、その内10人は共にベルリンから移住した演奏家たちだった。
同年から仏Les Discophiles Français レーベルで録音を開始すると、
フランスの一流演奏家と多くの交流が生まれることになる。
特に、フルート奏者のジャン=ピエール・ランパルを中心とする
パリ木管五重奏団のメンバーとの共演では素晴らしい録音成果を残した。
1960年前後には仏Le Club Français Du Disque レーベルに移籍。
大手レーベルから離れることで自由な選曲が可能となり、録音数は10倍近く増えた。
さらに本拠地ザールブリュッケン近く、ザールルイの地に録音設備が整い、
パリまで録音に出掛ける必要が無くなった事も録音数の増加に大きく寄与した。
しかしリステンパルトは1967年の演奏旅行中、
ポルトガルで心臓発作に襲われ、クリスマス・イブに死去してしまう。
彼の死はLe Club Français Du Disqueというレーベル、
それ自体の存続に関わるほどの重大な事件であったらしい。
運命を共にする様に翌1968年に15年間のレーベル活動を終了した。
楽団そのものは高名なチェリストであるヤニグロを指揮者に迎え継続したが、
1970年には首席ヴァイオリン奏者だったゲオルク·フリードリヒ·ヘンデルと
その妻で首席チェロ奏者でもあったベティ・ヘンデルを同時に自動車事故で失なう。
そして1973年にザールブリュッケン放送交響楽団に吸収される形で、
遂にザール室内管弦楽団は20年の歴史に幕を閉じるのである。
【演奏スタイル】
手兵であるザール室内管弦楽団を巧みに操り
ドイツの団体ながらフランス的な颯爽とした美麗な響きも兼ね備える、
稀有なサウンドを生み出した。
躍動感に溢れ、聴くものを愉快にさせる『魔法』をかけられる。
人真似ではなく、作品の真髄を引き出し『本物』を提示する。
協奏曲においてはソリストの実力以上の『手腕』を引き出す。
およそ残された録音を聴く限り、不得手とした曲が存在しない。
…そんな賞賛の言葉が尽きない天才的な指揮者なのだが、
同じくドイツとフランスという2つのエッセンスを兼ね備えた偉大なる音楽家、
モーツァルトの作品に関しては「絶品」という言葉以外が浮かばない。
リステンパルトが貫いた優雅で清冽な響きこそ、
モーツァルティアンが最終的に求める音なのではないだろうか。
ドイツ/ウィーン系の作曲家の大傑作録音が異国フランスで幾つも生まれ、
フランスのオーディオ文化を世界的なものにした要因の一つとして、
リステンパルトとザール室内管弦楽団の存在は欠かせない。
オーディオ史という意味では、確かに彼らは歴史を変えたのだ。
リステンパルトの在庫を見る
Ernest Alexandre Ansermet(1883-1969)
【主な活動レーベル】
DECCA
【経歴について】
スイス西部の街、ヴヴェイの生まれ。
父の影響を受けて当初は数学者としてローザンヌ大学の教授を務めていたが、
この就職先であるローザンヌの地での出会いが最初の転機となった。
作曲家エルネスト・ブロッホの薫陶を受け、1909年に指揮者に転身したのだ。
1910年にモントルーでデビューを飾り、そのまま当地のオーケストラの監督に就任。
この、活動の場をモントルーに移したことが第二の大いなる転機となった。
当地のカフェで作曲家ストラヴィンスキーと運命的な出会いを果たすと、
彼の紹介からバレエ・リュスの指揮者として抜擢、
一時期は専属指揮者として数々の初演を任される事になる。
第三の転機は1918年にジュネーヴにてスイス・ロマンド管弦楽団を創設したこと。
スイス・ロマンドとは「フランス語圏(ロマンス語圏)のスイス」という意味。
当然、国際的には無名な団体であったため経済的に苦しかった時期も長かったが、
地元の放送局オーケストラと合併したことで経済的な安定を得、
100年後の現在まで続く息の長いオーケストラとなった。
また、第二次大戦中にはワルターやフルトヴェングラー、
カール・シューリヒトなどドイツ本国で居場所を失った指揮者が
幾度となく客演指揮を務め、楽団の底力の向上の手助けをした。
そして戦争が終わると、第四の転機が訪れる。
同楽団と共に英DECCA レーベルとの契約を締結し、
アンセルメは大量の録音を残す事となる。
英国のレーベルだったDECCAはフランス作品においては
仏Ducretet Thomson や仏VEGA の音源を使用する事も多かったが、
フランス語圏の人間でありバレエ・リュスとの繋がりまで持つアンセルメは、
DECCAが自社録音でフランス作品を揃えるのに大いに貢献した。
しかし、アンセルメ最大の貢献といえるのは、
今もってなお世界最高峰といわれるDECCAのステレオ・サウンド、
その頂点に立つ SXL番台において名録音を数多く残した事に尽きる。
当時を知る録音技師Roy Wallaceによると、
1954年にDECCA社で初めてのステレオ試験録音を行った際、
数学理論にも明るいアンセルメが抜擢され、
彼の「文句なし!」の一言でサウンドが決定されたという。
【演奏スタイル】
アンセルメ本人の特徴としてはフランス語圏に留まらない国際感覚と、
その中で光るフランス的エスプリの機微が挙げられる。
フランス作品は元より、スペイン作品でもロシア作品でも
時に熱く、時に涼やかに、曲の魅力を聴き手に堪能させてくれる。
この国際的なバランス感覚こそバレエ・リュスや DECCAレーベルを惹きつけた、
アンセルメ最大の武器であったと思われる。
しかし、やはりスイス・ロマンド管弦楽団と併せて語らなければ片手落ちだろう。
創立者として、首席指揮者として長期間に渡って君臨し、
スポーツカーの様な凄まじいスピード感を持つ演奏集団に育て上げた。
当時、これだけ動きの俊敏なオケは他に類を見なかった。
内包されたエネルギーと大胆な表現が、曲の完成度といった次元を超えて感じ取れるのだ。
そしてアンセルメ × スイス・ロマンド管弦楽団 × DECCAのSXLサウンド、
この組み合わせは一つのブランドの様になっている。
一度はまってしまうと、何を聴いてもこれを基準に考えるようになってしまう。
しかし、これだけ筋肉質で骨太な音楽はそう滅多にある筈がない。
そして今日も、新たなアンセルメ・ファンが増えていくのである。
アンセルメの在庫を見る
André Cluytens(1905-1967)
【主な活動レーベル】
仏Columbia
La Voix De Son Maître(VSM)
【経歴について】
ベルギー北部の街、アントウェルペン(アントワープ)の生まれ。
出生時の名前はオーギュスタン・クリュイタンス。
地元アントウェルペンの王立ボウラ歌劇場(通称トネールハウス)で
指揮者を務めていた父アルフォンスから幼少時より音楽教育を受けて育ち、
22歳の時には早くも父の後を継いで第一指揮者となった。
そして1932年にフランスに移住、ここから名指揮者への道を歩み始める事になる。
トゥールーズのキャピトル劇場、リヨンのリヨン歌劇場、
ボルドーのグラン・テアトル歌劇場と首席指揮者を歴任、
遂には1939年にフランスへの帰化を決め、アンドレに改名した。
その後、1943年に首都パリに移住したのを契機として、
パリ音楽院管弦楽団(後のパリ管)との蜜月関係を築くこととなる。
同オーケストラ以外にもフランス放送交響楽団(ORTF)、
オペラ=コミック座などの音楽監督も兼任。
当然のことながら客演指揮にも引っ張りだことなり、
オペラ座やシャンゼリゼ劇場などでも八面六臂の活躍を見せる。
そして、世界的な音楽の中心地となっていたパリを沸かせる男を
各国のオーケストラが見逃すはずもなく、
ウィーン・フィル、ベルリン・フィル、チェコ・フィルなど、
世界中の様々なオーケストラが彼を客演指揮者として呼び寄せた。
1955年にはバイロイト音楽祭で演奏した最初のフランス人指揮者となり、
ドイツ人の為に築き上げてきた同音楽祭の歴史を塗り替える事となった。
主催者であるヴィーラント・ワーグナーも、最大の賛辞を贈っている。
「クリュイタンスの響きは、エレガントで、クリアで、
ニュアンスがあり、カラフルで、威厳に満ちていた。
それは洗練された一流のオーケストラが持つ響きの中でも、
最も崇高なものだった。」
【演奏スタイル】
一言で表すならば「フランスそのもの、パリそのもの」である。
パリ音楽院管弦楽団を1946年から没年まで率い、
オーケストラに於けるフレンチ・スタイルを確立させた。
後継団体であるパリ管弦楽団(パリ管)は、
指揮者の国籍を問わず一貫してフランス的な音を出すことで知られている。
この『フランス的』である清冽で明朗、色彩豊かなサウンドは、
先代のミュンシュとクリュイタンスが作り上げたものであり、
現代に至るまで続く大いなる系譜なのである。
自由奔放、なのに曲としての完成度は高く、
匂い立つ様な妖しい濃厚さと、清流の如き清らかさを同時に表現する。
押し付けがなく、力みもないが、エネルギーはあり、
個々のフレージングが軽妙にして爽やか。
こういった幾つもの相反する要素を一つに料理してしまう、
このさじ加減こそクリュイタンスならではの手腕。
そして、この手腕は協奏曲でも十二分に発揮される。
マルグリット・ロンとのフォーレおよびショパン、
その弟子サンソン・フランソワとのラヴェルなど、
後に決定盤と呼ばれる様な数々の名演を繰り広げた。
また、客演でも数々の名指揮を見せている事を忘れてはならない。
例えばベルリン・フィル初となるベートーヴェンの交響曲全集録音である。
EMIグループは首席指揮者のカラヤンではなくクリュイタンスを起用した。
※バイロイトの成功を聞きつけた DECCA が引き抜きを画策、
フランスEMIグループがクリュイタンスを自社に繋ぎ止めるために
系列会社の独ELECTROLA から根回ししたとされる。
フランス音楽を得意とするベルギー人が、
ドイツ人のオーケストラでドイツ人作曲家の代表作を指揮する…。
そんなシチュエーションでもクリュイタンスは流石だった。
意外な程の迫力感に溢れながらも、流麗で押し付けがましいところが無い。
技術と感情とのバランスが完璧に整ったベートーヴェンを作り上げたのである。
クリュイタンスの在庫を見る
Carl Adolph Schuricht(1880-1967)
【主な活動レーベル】
La Voix De Son Maître(VSM)
Concert Hall
【経歴について】
ポーランド北部の街、グダニスク(ドイツ語ではダンツィヒ)の生まれ。
6歳から隣国ドイツのギムナジウムに入学すると、以降はドイツを本拠とした。
音楽人生の転機となったのは1912年から1944年まで続いた、
ドイツ中央西部のヘッセン州ヴィースバーデン市の音楽監督への就任である。
ここでシューリヒトはヴィースバーデン市立管弦楽団を手兵とし、
ドイツ好みの古典派やロマン派に留まらず、現代音楽も好んでプログラムに取り入れた。
これには1906年のマーラー「交響曲第6番」の初演を目にした事が大きかった様である。
1913年に指揮したマーラーの交響曲第8番「千人の交響曲」は、
ドイツのみならず欧州中にシューリヒトの名前を轟かせる。
翌年にはロンドンやミラノに招聘されるなど、順風満帆のキャリアが始まる筈であった。
…しかし、ミラノ・スカラ座出演の直後にサラエボ事件、そして第一次世界大戦が勃発。
彼の名が再び音楽史に戻ってくるまで、実に7年の歳月を必要とした。
1921年、自身が発起人となったグスタフ・マーラー音楽祭を開催、
5月にはベルリン・フィルへの客演と立て続けに敬愛するマーラー作品を演奏。
結果、1920年代には「マーラーと云えばシューリヒト」という揺るがぬ評価を
国内外から受けていたシューリヒトだった…が、またしても彼を苦難が襲う。
1932年にナチスが第一党となると、ユダヤ系だったマーラーの曲が禁止された。
国内の活動を続けながら、それでも国外では変わらずマーラーを演奏し続けていたが、
第二次大戦が激化する1944年には遂にゲシュタポに追われスイスの地に亡命する事となる。
2度目の終戦がようやく訪れると、その後はウィーン・フィルとの関係を深める。
ナチス側を疑われた指揮者や楽団員が次々と退団していく中、立て直しに尽力。
アメリカを始めとした世界ツアーにも首席指揮者として同行し、成功を収めた。
1965年8月、齢85歳にして生涯最後となる指揮となったのも、
ウィーン・フィルとのザルツブルク音楽祭での演奏だった。
【演奏スタイル】
誤解を恐れず言えば、独特のテンポ感を持つ御仁である。
颯爽と吹き抜けるつむじ風の様なスタイルで、
大型の推進装置をまとったロケットの如く、速足で駆け抜ける。
そこにブレない『魂』を感じてしまうので、聴いている方も曲に入り込んでしまう。
「疾走するサウンド」「疾走するオーケストラ」の枕詞を聞いて、
スイス・ロマンド管弦楽団を連想される方も
DECCA愛好者を中心に少なからず居るだろう。
実はスイスへの亡命中、シューリヒトはアンセルメの誘いを受けて、
60回以上に渡り客演指揮者として同楽団に携わっているのだ。
あの類稀なるスピード感の背景には、シューリヒトの影響もある事が想像に難くない。
ただし「テンポ感が早い=情感や芸術性が薄い」という事では決してない。
シューリヒトの後半生の評価を絶対的にしたのは、
1956年1月、76歳の時にウィーン・フィルを振ったモーツァルトである。
前年、戦火の影響から消沈していた名門ウィーン・フィルを
シューリヒトが一喝し奮起させたとの逸話も手伝い、
(本拠地だったウィーン国立歌劇場は空襲で焼け落ちたままだった)
偉大なる作曲家の生誕200周年を祝うに相応しい、
あまりに美しいモーツァルトは観衆から大絶賛を受けたのである。
また、よくある誤解で「遅咲きの指揮者」と評される事が多い。
しかし、経歴を見ていただければ判るが2度の戦争が影響して、
オーディオ文化と上手く関われなかった、と捉えるのが正しいだろう。
VSM でのウィーン・フィルとの共演は名盤を幾つも残したが、
商業主義的なEMIグループとは上手く折り合いが付かず馘首されてしまう。
移籍先の Concert Hall では一流のオケとの共演が難しく、
パリ音楽院管弦楽団以外とは秀演を上手く残せなかった。
しかし、ドイツの片田舎のヴィースバーデン市を音楽の都に変え、
ベルリン・フィルを含めたドイツ各地のオーケストラを率い、
スイス・ロマンド管弦楽団にアンセルメと共に携わったのは、
決して老人になってからの経歴ではない。
彼の『魂』が老齢になろうとも色褪せなかっただけの話なのである。
晩年の指揮を見た評論家、ロジェ・ヴァンサンの言葉を最後に紹介したい。
「この舞台を弱々しく歩く老音楽家が、いざオーケストラの前に立った時、
老人の影はかき消えて、その若々しさと信念とで全てを変えてしまったのだ。」
シューリヒトの在庫を見る
Gennady Nikolayevich Rozhdestvensky(1931-2018)
【主な活動レーベル】
MELODIYA
【経歴について】
旧ソビエト連邦、モスクワ生まれ。
父親は指揮者でモスクワ音楽院で教授も務めたニコライ・アノーソフ。
そして母親はボリショイ歌劇場所属のソプラノ歌手、
ナターリャ・ロジェストヴェンスカヤという、音楽家の血筋に産まれた人物。
ちなみに「ロジェストヴェンスキー」は芸名で、
本名はゲンナジー・ニコラエヴィチ・アノーソフ。
高名過ぎる父の苗字が自身の活動に影響を与えるのを懸念して、
母方の苗字を男性系にして芸名にしたとのこと。
※スラブ系の命名法は、名前→父親の名前の変化形→苗字という並びに、
それぞれに男性形、女性形の変化が加わるのが基本。
父親の名前も同じセルゲイだったセルゲイ・プロコフィエフを例にとると、
セルゲイ(名前の男性形)
・セルゲエヴィチ(=セルゲイの息子)
・プロコフィエフ(苗字の男性形)がフルネームである。
仮にもし、プロコフィエフが女性だったら以下の通りになると思われる。
セルゲエワ(セルゲイの女性形・架空の名前)
・セルゲエヴナ(=セルゲイの娘)
・プロコフィエワ(苗字の女性形)
モスクワ音楽院で父アノーソフに指揮法を、レフ・オボーリンにピアノを師事し、
18歳で母の職場でもあった首都モスクワのボリショイ歌劇場にて、
プロコフィエフのバレエ「シンデレラ」を振って指揮者デビュー。
その後、20歳の時に指揮したチャイコフスキー「くるみ割り人形」の公演で名声を勝ち取る。
晩年のプロコフィエフは「天才を超えた天才」と彼を大絶賛した。
その後はボリショイ歌劇場を主戦場としながら、
モスクワ放送o.など国家を代表するオケの指揮者としてキャリアを形成。
70年代に王立ストックホルムpo.の音楽監督に就任して以降は西側にも活動の幅を広げ、
BBC交響楽団、ウィーン・フィルと世界的なオケの首席指揮者まで務めあげた。
この縦横無尽の活躍に当時のソ連政府は亡命を恐れ、
遂にはソヴィエト文科省フィルというオーケストラを新設するまでに至った。
このロジェストヴェンスキーの個人オケとすら言える
文科省フィルを手兵に従えた事実は殊のほか大きく、
ショスタコーヴィチ、グラズノフ、ブルックナーなどの交響曲全集、
妻のポストニコワをソリストに招聘したプロコフィエフのピアノ協奏曲全集など、
ソヴィエト連邦という国が消滅するまでの10年間、オーディオ史に多大なる成果を残した。
また、共産圏の生まれながら順応性も高く、
ベルリン・フィル、コンセルトヘボウ、ロンドン・シンフォニー、
クリーブランド管弦楽団、イスラエル・フィルなど数多くの客演をこなし
名実ともに20世紀の「東側」を代表する指揮者へと大成していくのである。
ロシアのクラシック史を振り返った時、
チャイコフスキー、ラフマニノフ、プロコフィエフなど作曲家が全盛だった19世紀を経て、
オイストラフ、リヒテル、ホロヴィッツ、ロストロポーヴィチ等、
実演家の才能が一挙に開花する20世紀が訪れる流れがある。
この実演家の時代を牽引した指揮者こそ、ロジェストヴェンスキーだった。
【演奏スタイル】
父アノーソフと二代に渡り、ソ連MELODIYAレーベルを牽引した最重要人物の一人。
日本では「爆炎系」の指揮者として紹介される事が多いが、
そもそも旧ソ連の古い指揮法では爆炎系を至上としていた節が有るので、
ロジェストヴェンスキー本人の嗜好だったとするのには違和感が有る。
世間の風聞に寄らず彼の経歴を見てみると、
ロシアン・バレエ本家のボリショイ歌劇場でデビューし、
後年にはウィーン・フィルの首席指揮者まで務めた。
「情緒的」あるいは「標題的」な楽曲は、むしろ得手だったと考える方が自然だろう。
晩年のインタビューによると本人はイギリス作品を特に愛していたそうである。
冷戦が続いていた時代、本来の音ではない粗悪な日本ライセンス盤を聞いて、
MELODIYAレーベルと、その代表格だったロジェストヴェンスキーの評価が
誤った方向に向かってしまったきらいが本邦には有る。
近年になりロシア盤を聴いた結果、MELODIYAレーベルの再評価と共に
ロジェストヴェンスキーを誤解をしていた事に気付く人も少なくない。
国家を代表する指揮者として残した数多くの録音を聴くと、
若年期の爆炎時代、地位を得て充実した音を鳴らしていた時代、
そして、よりコマーシャルな西側風なサウンドへ変化していく流れが見える。
特に、自由に振れるソヴィエト文科省フィルの設立は1981年のこと。
アナログからデジタルへと録音史が変遷していく過渡期でもある。
そして、デジタル録音という未来の新技術を担当させられるのは
国家を代表する指揮者ロジェストヴェンスキー、という流れは当然だった。
しかし、これは音質の向上とイコールとは安易に言えないのだ。
ステレオ然り、デジタル然り、「新技術」に慌てて飛びついた、
手放しには賞賛しかねる録音は、
ロジェストヴェンスキーに限らずレコード史には多い。
或る意味でデジタルの実験台だったロジェストヴェンスキーに対し、
例えばロシアの超凄腕ピアニストであるカミショフは
国家的、政治的には重要な人物ではなかった様で1986年に於いてもアナログ録音だった。
だが、音質的な面で言えば逆にこれが功を奏して、
前人未到の域に有る彼のピアニズムを生々しく記録出来たともいえる。
ここにもまた、ロジェストヴェンスキーの評価が左右される「裏側」がある。
交響曲全集など作品のライブラリ化を達成した功績は非常に大きい。
(たとえ国策だったとしても、である)
ただ、それだけでロジェストヴェンスキーの評価をしてしまわず
小品や室内楽、バレエなど、敢えて少し横道に逸れてみることで、
日本の定評とは違う本来の彼の魅力に出会う事が出来る筈である。
個人の人間性で伝え聞くのは、特に晩年はリハーサルが大嫌いだったという逸話。
通しリハーサルにしか来ず、お決まりの言葉は「break」だったそう。
要は「コーヒー・ブレイク」、あるいは英国なら「ティー・ブレイク」である。
「休憩」という言葉以外は殆ど話さなかったというのだ。
しかし同時に語られるのは、そのバトン・テクニックの巧みさである。
指揮棒で意図を伝えられてしまうなら、長いリハも、そして言葉すらも不要だった。
あるいは馴染みのオケならば、指揮棒すら不要だったという。
そんな、ある意味では奇矯に見える立ち振る舞いの伝説が現代にも伝わっている。
ロジェストヴェンスキーの在庫を見る
Igor Borisovich Markevich(1912-1983)
【主な活動レーベル】
米DECCA
His Master`s Voice(HMV)
仏Columbia
PHILIPS
Deutsche Grammophon(DGG)
※経歴が多岐に渡るため時系列順
【経歴について】
現ウクライナ、キエフ(キーウ)生まれ。
ピアニストであるボリス・マルケヴィッチと画家の娘ゾイア・ポキトノヴァを父母に持つ。
また曾祖父のアンドレイは帝政ロシア時代の国務長官であり、
ミルシテイン兄弟と共にロシア音楽協会とサンクトペテルブルク音楽院を創設、
ロシアの音楽文化、音楽教育を牽引した人物だった。
2歳の時にパリ、3歳の時にスイスと、
第一次大戦の戦火から逃れる様に移住すると、父の元でピアノ教育を受ける。
若かりしクララ・ハスキルのコンサートに母に連れていかれたりもした様である。
そのスイスで、同地出身の巨匠ピアニスト、
アルフレッド・コルトーとの出会いを果たしたのが第一の転機。
コルトーは自身が創立したエコール・ノルマルにマルケヴィチを自費で招聘し、
ナディア・ブーランジェを通し最高峰の音楽教育を施した。
このブーランジェは「第二の母」とも言うべき存在だったらしく、
「厳格さ、徹底こそが音楽の熱情を人々に伝える手段」という
ブーランジェ女史一流の音楽観を叩き込まれる事となる。
そして1928年マルケヴィチ16歳の年に、次の運命的な出会いが彼を待ち受ける。
バレエ・リュスの主宰、セルゲイ・ディアギレフとの邂逅である。
新しい演目を書ける作曲家を探していたディアギレフはマルケヴィチの才能に惚れ込み、
オーケストレーション分野での教育を受けさせ、幾つかの曲を彼に書かせた。
作曲方面でのマルケヴィチの活躍についての詳細は割愛するが、
マルセル・メイエルが初演を務めた「ピアノと小オーケストラのためのパルティータ」と、
バルトークから「現代音楽で最も印象的な個性」と評されたバレエ音楽「イカロスの飛翔」
この二作への評価から想像するにブーランジェ譲りの才能を発揮していた様である。
指揮の方では、ピエール・モントゥーを師と仰いだ。
ペトルーシュカ、牧神の午後への前奏曲、春の祭典など、
バレエ・リュスの音楽を支えた指揮者だったモントゥーは
若手指揮者の育成に力を入れる為に私塾としてエコール・モントゥーを開いた。
バレエ・リュスと親交の深かったマルケヴィチも薫陶を受け、
モントゥーが次席の指揮者を務めていたコンセルトヘボウ管弦楽団で
20歳にして指揮者デビューを果たす事となる。
その後、第二次大戦の直前にイタリアの皇族、
しかもローマ教皇の血を引くドンナ・トパジア・カエターニと結婚をすると、
戦中はイタリアのパルチザン、反ファシズムの過激派として活動を行った。
一説に拠れば、活動への傾倒は周囲が驚くほどであり、
戦後の1978年に起きたアルド・モーロ元イタリア首相の誘拐殺人にも、
マルケヴィチが組していたのではないかと囁かれているほど。
第二次大戦の末期に大病を患った後は指揮者に専念。
戦後ほどなくして世界的規模での指揮活動を始めた。
首席指揮者としてはフランスのラムルー管、
モナコのモンテカルロ・フィルの歴史に名を刻むが、
他を凌駕したのが、その録音遍歴である。
世界を股にかけ、数多の名オーケストラを率いて
名盤の数々を作り上げた手腕は類を見ない偉大な功績といえるだろう。
また、録音活動と並行して教育活動にも熱心だったようで、
ザルツブルクのモーツァルテウム音大での教え子には、
レコード期の古典復興に大いに貢献した
ジャン=フランソワ・パイヤール、ヘルベルト・ブロムシュテットがいる。
激動の生涯を送ったマルケヴィチは最後もまた唐突で、
1983年にフランス南部、地中海を臨むアンティーヴの地で
心臓発作により急死を遂げた。
奇しくも、最後のコンサートは生まれ故郷のキエフ公演だったという。
余談となるが、先述した妻ドンナとの間に生まれた息子オレグは
イタリア皇族の血を残すためオレグ・カエターニの名を用い、
70年代から現代に至るまで指揮者として活動を続けている。
そしてオレグの恩師もまた、父と同じナディア・ブーランジェだった。
【演奏スタイル】
他に類を見ない録音実績を持つ、まさに「万能型」の指揮者である。
そもそも振るったオケ自体が東西を問わない途轍もない量で、
首席だったラムルー管を筆頭に、ロンドン交響楽団、ゲヴァントハウス管弦楽団、
ベルリン・フィル、モスクワ・フィル、ソビエト国立管弦楽団、
そしてEMIの録音専門オケであるフィルハーモニアにも当然の様に携わった。
現代にも残る、舞台裏の職人への最大の賛辞として
『ファースト・コール』という言葉がある。
音楽を含めた芸術イベントの「演出家」や「舞台監督」の様な裏方を選ぶ際、
関係者一同から「成功請負人」と認められ、
スケジュールの争奪戦になる人物への最高の賞賛に使われる言葉である。
レコード制作の流れで言えば、
商品企画として曲目やソリストをレーベルが選定した後、
座組みが自社で殆ど完結している録音技師のチームとは別に
オーケストラと指揮者の選定が起きる事は想像しやすいだろう。
言わずもがな、マルケヴィチの異能とは正しく此処に有ると思われる。
彼こそがLP期における『ファースト・コール』の指揮者だった事は疑い様がないのだ。
とある指揮者は手兵を用いて自己のサウンドを最大限に追及した。
とある楽団は自己のアイデンティティを頑なに守り、指揮者の人選にすら口を出した。
マルケヴィチには、殆どそういった拘りが見られない。
空恐ろしい程に、曲目も、オケも、挙げ句にはレーベルも飛び越えて、
前人未到といえる数の録音を繰り広げてしまったのだ。
先天的な東側の出自と後天的に培われた西側的な感性を用い、
ほとんど如何なる楽曲を振っても名盤クラスの録音を残した。
交響曲、協奏曲から宗教曲、バレエにオペラ、
果ては自身が編曲した「音楽の捧げ物」B.1079など、
縦横無尽という言葉がこれほど似合う指揮者もいないだろう。
これだけの万能性は、もはや「異才」と呼ぶほかに無い。
そして、そんな万能な人物だからこそ面白いのが、
もしや不得手が有ったのでは?という可能性である。
オケで言えばウィーンフィル、作曲家で言えばシューベルト。
他のオケや作曲家に比べて圧倒的に少ない録音を見るに、
相性がよほど悪かったのかも知れないのだ。
万能型の音楽家の常として「節操が無い」と誤解されがちだが、
小手先で「こなす」様な人物像とは全く無縁である。
時に思索的に、時に熱情的に、高い音楽性を保ち続けた。
「厳格さ、徹底こそが音楽の熱情を人々に伝える手段」という、
第二の母の教えたまいし信念が、いつもマルケヴィチを支えていたのだ。
マルケヴィチの在庫を見る
Otto Nossan Klemperer(1885-1973)
【主な活動レーベル】
VOX
英Columbia
【経歴について】
現ポーランドのヴロツワフ生まれ。(当時の呼称はドイツ帝国ブレスラウ)
ボヘミア王国プラハのユダヤ人ゲットー出身である父ネイサンと、
ハンブルク生まれのスペイン系ユダヤ人である母アイダ、姉と妹という5人家族だった。
フランクフルト芸大からベルリン芸大へと進む学生時代を送り、
ベルリンの地でハンス・プフィッツナーから指揮と作曲を師事した。
転機が訪れたのは20歳の時。
マーラーの交響曲2番、通称「復活交響曲」の公演に携わったのである。
同曲ではメインのオーケストラとは別に「Fernorchester」と名付けられた、
舞台裏に隠れて遠鳴りを表現する2つ目のオーケストラを活用する。
この別動隊の指揮を振るう事となったクレンペラーは、
作曲家マーラーと知己を得、同曲のピアノ編曲版を後に披露するなど交流を深める。
1907年にはマーラーの紹介からプラハ歌劇場の合唱指揮者に就任。(後には音楽監督に昇進)
1910年にはマーラー畢生の大作、交響曲10番「千人の交響曲」の初演も手伝う事となった。
そして、20代後半以降のクレンペラーは、歌劇場を中心に凄まじい活躍を見せる。
ハンブルグ歌劇場(1910–1912)、バルメン歌劇場(1912–1913)、
師であるプフィツナーの代役として仏国ストラスブール歌劇場と
付随するストラスブール・フィルの音楽監督(1914–1917)、
再びドイツに戻ってケルン歌劇場(1917–1924)、ヴィースバーデン歌劇場(1924–1927)、
そしてベルリンのクロル歌劇場、通称「クロルオーパー」(1927-1931)と、
オペラの指揮において八面六臂の活躍を見せた。
特にクロルオーパーでの活動には並々ならぬ情熱を注いだらしく、
新時代のオペラを追求するため、現代音楽を次々と演奏した。
シェーンベルク、ヒンデミット、ストラヴィンスキー、ヤナーチェク等、
「同時代のすべての現代作曲家の作品を指揮した」と評されるほど。
舞台美術においてもバウハウスの教員を招聘したり、
果てはシュールレアリスムの大家キリコまでが参加している。
しかし、このあまりに革新的な音楽活動は聴衆の意見を二分、
最終的には「経済的な理由」として議会から1931年に歌劇場の廃止を決定された。
これはクレンペラーにとっては到底納得がいかない決定であり、訴訟まで起こしている。
そして運命が変わる1933年が訪れた。
ヒットラーの首相就任とナチス政権の発足である。
よりにもよってクロルオーパーを国会議事堂とした彼らにより、
クレンペラーは文化ボリシェビストと認定、演奏活動を禁止された。
進歩的な感性を持つユダヤ人芸術家という存在は、
ナチス政権にとって許しがたいものだったのだろう。
国民啓蒙・宣伝大臣を務めドイツ国内の劇場を統制したゲッペルスの日記には、
「夕方、タンホイザーを鑑賞。クレンペラーはこの曲を全く理解していない。
ユダヤ人にはワーグナーが理解できないどころか、憎んでさえいるのだろう。」
『Lexikon der Juden in der Musik(音楽に携わるユダヤ人百科)』なる書籍には、
「クレンペラー:ドイツの誇る傑作を意図的に歪める事を主な生業とする指揮者」とある。
当然ながら、こんな政府下では生活すらままならないため
同年4月からはベルリンを離れチューリヒ~ウィーンと移住し、
結果、8月にはウィーン・フィルを率いザルツブルグ音楽祭に初出演する栄誉を得た。
10月になると米国ロサンゼルス・フィルが音楽監督として招聘。
少なからず迷いは有った様だが、1935年には家族と共にカリフォルニアに移住した。
しかし、この米国の地では幾多の苦難と挫折がクレンペラーを待ち受けていた。
フィラデルフィア管弦楽団、またはニューヨーク・フィルの主席指揮者を狙っていたが、
前者にはユージン・オーマンディが、後者にはジョン・バルビローリが就任。
特にニューヨーク・フィルに関しては前任のトスカニーニがクレンペラーを推挙していた為、
その衝撃は大きかった事をクレンペラー自身が手紙で書き残している。
更に不幸は重なる。1939年に「小さなオレンジ」程もある脳腫瘍が見付かり、
手術の結果、部分的な麻痺と深い躁鬱病が後遺症として残った。
療養施設を脱走して酒場に居た所を写真誌にすっぱ抜かれるなどの事件も起こし、
ロサンゼルス・フィルも解任されてしまう。
もはや米国での名声は望むことも出来ない事態となってしまった。
第二次大戦が終結すると、クレンペラーは欧州に活躍の場を移す。
過去にマーラーが監督をしていたハンガリー国立歌劇場の音楽監督に就きつつ、
ベルリン放送交響楽団、デンマーク王立管弦楽団、モントリオール交響楽団、
ケルン放送交響楽団、コンセルトヘボウ管弦楽団など様々な客演を行った。
が、ここでもまた体制との軋轢がクレンペラーを襲う。
1950年初頭、米国では「赤狩り」「マッカーシズム」の風が吹き荒れ、
左派的な人物だったクレンペラーもその標的となった。
ソ連の衛星国家だったハンガリー国立歌劇場での活動歴も悪く働き、
既に米国籍だったクレンペラーは1952年にパスポートを剥奪されてしまうのだ。
仕方なくモントリオール交響楽団などでの活動をメインにしていたが、
1954年に欧州の地に戻ることを決意し、ドイツ市民権を回復した。
ただし、亡命に近かった米国への移住と違い、欧州への帰還には勝算が有った。
ロンドンへの客演の際、EMIの名プロデューサーであるウォルター・レッグが
クレンペラーの演奏に惚れこみ契約を熱望したのである。
レッグの私兵であるフィルハーモニア管弦楽団を任せていたカラヤンが、
フルトヴェングラーの逝去を契機としてDGGレーベル傘下のベルリン・フィルに移籍。
更には1956年には次代のスター候補だったグイード・カンテッリが、
突然の飛行機事故により急逝してしまう。
結果、名実ともにフィルハーモニア管弦楽団の長となったクレンペラーは
1959年には終身首席指揮者に就任する。
なんと1963年に創設者レッグがEMIから脱退、翌年にはパトロンも辞めてしまうが、
この緊急事態にも楽団員と団結し、ニュー・フィルハーモニア管弦楽団を創設した。
60代後半という老齢になってからの出会いだったが、
フィルハーモニア管弦楽団がその晩年を充実させた事は間違いない。
毀誉褒貶にまみれ、根無し草の様な音楽人生を送り続けたクレンペラーに
他の巨匠と同様の世界的名声を与えてくれたのが、このオーケストラだったのだ。
その後は1970年にイスラエル放送局交響楽団をエルサレムで指揮し、
ほぼ同時にイスラエルの市民権を獲得。
翌1971年に体調不良を理由に全ての指揮から引退した。
そして1973年スイスはチューリッヒの地で、88年に渡る波瀾の人生に幕を閉じた。
【演奏スタイル】
雄大で荘厳なスケールで楽曲を描く「巨匠」の名に相応しい指揮者である。
格調高いサウンドを持ち、演奏者各々に唄わせるというより
トータルで楽曲の世界を壮麗な建造物のように構築していく印象で、
個性を越えた大きな意志の力を感じさせてくれる。
重いテンポで濃厚な色彩感を描き出すのを得手とするため、
大規模作品を振らせれば、まさに極上。クレンペラーの独壇場である。
…というのが一般的な評価で、それも確かに間違いではない。
が、それだけの指揮者と思うと見落としをしかねない。
オーディオ・ファンが名高きSAX番号に魅せられるのは理解できるが、
レッグとの出会い以降だけでは、音楽家クレンペラーを語る事は出来ないのだ。
例えば名演とされるステレオ期の「田園」こそクレンペラーと思っている方は多いが、
若かりし1950年代頃の録音を聴くと端正だが情感に富んだスタイルで、
重厚な曲を振ってもどこか華やいだ印象を感じさせる。
VOX時代~初期の英COLUMBIAにはクレンペラーの残したモノラル録音が相当あり、
どの作品も今聴いてなお素晴らしく、レッグが惚れこんだ理由が分かるだろう。
経歴を見てわかる通り、本来は前衛的な音楽を愛する人物だった。
しかし、ドイツとアメリカで受けたある種の迫害がクレンペラーを変えた。
聴衆と評論家連中からは現代音楽への理解が得られず、
「ドイツ作品を熟達に振るうドイツ人マイスター」としての立場を求められたのだ。
海外ではクレンペラーが年齢を経るにつれテンポを落としていった事実と、
初期の録音においては他の指揮者よりテンポが早かった可能性が示唆されている。
また、それは楽曲の構造への理解が変遷したのではなく、
理解はそのままにテンポを落としていったのが最もユニークな点だと語られる。
日本では奇矯な振る舞いを矢鱈と取り沙汰してしまうフシがあるが、
初期におけるドイツ的でありながら清冽で颯爽としたサウンドも、
後期におけるデモーニッシュで、劇的な演出がなされたサウンドも、
好き嫌いを云々する以前に、一つの個性として認めざるをえない。
特にベートーヴェンの交響曲に関しては、
ここまで雄大なスケールで録音した指揮者は当時いなかった。
あのDECCAの中にさえ、この時代に一人で全集を作り、
トップセールスを成し遂げた指揮者はいなかったのだ。
コロンビア社の大黒柱であり、社を支えた重要な指揮者であった。
世界中の人に愛聴される、繰り返し聴いても新鮮さの落ちない歴史的傑作を
クレンペラーが作り上げた事実だけは間違いない。
彼の残した5番「運命」は金の円盤に収められ、
ボイジャー探索機という揺りかごに乗り、
太陽系を離れ今日も宇宙を旅している。
クレンペラーの在庫を見る
Károly Ferenc Fricsay(1914-1963)
【主な活動レーベル】
Deutsche Grammophon(DGG)
【経歴について】
ハンガリーの首都ブダペスト生まれ。
軍楽隊のバンドマスターだった父アラヨス・リハルト(リカルト?)は、
各地を回りクラシック音楽の普及に努めた、ハンガリーを代表する指揮者だった。
そんな父から幼少期より音楽教育を受けたフリッチャイは、
自分と同じ名を持つリスト・フェレンツ音楽大学(リスト音楽院)に6歳にして入学。
ハンガリーを代表する音楽家であるバルトーク、コダーイ、ドホナーニの薫陶を受けた。
ここで数々の楽器と作曲、指揮法を学んだ後、1933年に同音楽院を卒業すると、
ハンガリー南部の街セゲドの軍楽隊の副指揮者として活動を始める。
その後のキャリアは順調だった様で、1935年にはセゲド交響楽団の指揮者に就任。
1936年からはセゲドの国立歌劇場や野外劇場でも指揮を執った。
更には軍内においても1943年には陸軍の最高指揮者の栄誉を受けた。
状況が変わったのは1944年のこと。
1930年代後半からナチス・ドイツの影響下にあったハンガリーにおいて、
ナチスの傀儡政権である国民統一政府が樹立。
そして母方がユダヤ系だったというフリッチャイは、
過去にユダヤ系音楽家を優遇して軍法会議にかけられた過去があった。
ゲシュタポに狙われているという友人からの警告を受け、
セゲドの地から逃亡し、ブダペストに妻子ともども潜伏する事となった。
ただ、早くも翌1945年にはハンガリー全土からドイツ軍が掃討され、
ハンガリーはペレストロイカに至るまでソ連の影響下に入る。
この1945年からフリッチャイは首都ブダペストにある
ハンガリー国立歌劇場の首席指揮者に就任。
ここでアメリカから主戦場を欧州に移していたクレンペラーと邂逅した。
この出会いから1946年のオーストリア・ザルツブルク音楽祭において
体調に問題を抱えていたクレンペラーのアシスタントを務めた後、
翌1947年には完全に降板してしまったクレンペラーに代わってウィーン・フィルを指揮した。
このザルツブルク音楽祭での評判は非常に良かった様で、
「初演の翌日から彼は世界中で話題になりました。オファーが殺到したのです。」
そんな風に当時の音楽監督が語っている。
世界的な名声を得たフリッチャイは1948年からベルリン放送交響楽団(RIAS)と、
ベルリン国立歌劇場の首席指揮者に就任。
録音においても独DGGレーベルと契約を果たした。
1950年には英国およびアルゼンチン、1951年にはイタリア、オランダ、
1953年に至ってはパリ、スイス、アメリカと次々にデビューを果たし、
まさに世界を股にかける指揮者として充実した日々を送った。
あまりの多忙の為かベルリン国立歌劇場の指揮者は退任したが、
1958年に今度はバイエルン国立歌劇場の音楽総監督に就任。
そして遂に、ベートーヴェンの交響曲の全集録音に取り掛かる事となる。
…が、この大仕事を成すには、残された時間は余りにも少なかった。
同年11月末に体調を崩すと胃癌との診断を受け、
2回の手術を経て翌1959年9月まで静養を余儀なくされる。
静養から明けるとベルリン放送交響楽団(RIAS)と活動を再開、
ドイツ初のラジオでのステレオ放送に貢献。
1961年はメニューインとの欧州ツアーやザルツブルク音楽祭と精力的に飛び回った。
同年はベルリンの壁が出来た年でもあり、
結果としてベルリンの西側で唯一となってしまった歌劇場、
ベルリン・ドイツ・オペラの復活コンサートでも指揮を振るう。
これは史上初となるテレビでのオペラ生放送だったそうで、
これらの功績によりドイツ功労十字勲章を受ける。
しかし、この年の冬に再び体調を崩し再手術。
12月7日のコンサートを最後に療養に入るが二度と指揮台に戻る事はなく、
1963年2月20日、スイスはバーゼルの地で胃癌(※)により天に召された。
わずか48歳、あまりにも早過ぎる死だった。
※日本では白血病を死因としている情報が殆どだが、非常に多くの疑義がある。
フリッチャイ公式サイト、出生地のハンガリー、活動の中心だったドイツ、
いずれの資料にも「白血病=Leukémia」という単語は見られない。
米国の音楽評論家であるRichard Freed氏がワシントン・ポスト紙に寄稿した、
フリッチャイの死因を白血病とした英語の記事が一件存在しているだけである。
そもそも内科的治療が基本である白血病の患者だとしたら、
最低3回は受けた記録が残る「手術」とは一体どんな手技だったのか。
1959年に初めてヒトでの臨床実験が行われた骨髄移植に挑んだのなら、
ドイツ国内にニュース記事がないのは余りにも不自然である。
ハンガリーとドイツの多くの資料に見られる『Gyomorrák』あるいは『Magenkrebs』
つまり「胃癌」が死因だったのが客観的な真実だろう。
あるいは、合併症である「胆嚢への穿孔」というのが直接の死因の可能性も高い。
他方、同郷の師であるバルトークが白血病だった事は間違いが無く、
Googleでは『Leukémia Bartók』で50万件以上の検索結果が得られる。
上記した評論家のRichard Freed氏が師弟を取り違えて記事を書き、
アメリカの一部と日本に誤った伝聞が広まった疑いが強い。
【演奏スタイル】
独DGGレーベルと首都ベルリンの音楽を支えた、
大陸的で大らかなサウンドを持つ指揮者である。
ベルリン・フィルには無い甘美さを持つベルリン放送交響楽団を率い、
実に繊細で、荒っぽさが微塵もない、一つの完成された美意識を作り上げた。
もちろん、この美意識はウィーン・フィルとの共演でも存分に発揮され、
ザルツブルク音楽祭での圧倒的な評判から追加コンサートを開催する必要まで起きたほど。
また、若年からの師であるバルトークの影響からか近代的な感覚にも優れ、
ハイドンの交響曲から当時の新作だった現代音楽までレパートリーとしていた。
作曲家としてのお気に入りはバルトークとモーツァルトだったと伝わるが、
活躍を見るとロッシーニからワーグナーまでオペラにも精通しており、
また出身地である東欧の作曲家であるドヴォルザークやリストも得手とした。
特に、才媛ヨハンナ・マルツィをソリストに迎えたドヴォルザーク:Vn協奏曲Op.53は、
今なお音楽史に燦然と輝く不朽の名盤として名高い。
そして資料を紐解くと分かるのが、
共演者たちがフリッチャイの「感性」に驚き、心酔していく姿である。
ソプラノ歌手のマリア・シュターダー曰く、
「私が最も驚いたのは、彼の歌に対する直観的な感性でした。
歌手としての訓練を受けたことも、歌唱の生理学的プロセスを研究したことも無いのに、
人間の声に対する彼の共感は完璧で、幾つもの大事なアドバイスをくれたのです。
それらは私がキャリアを進んでいく上で、本当に大きな助けになりました。」
バリトン歌手のフィッシャー・ディースカウ曰く、
「私がドン・カルロでオペラ・デビューを飾ろうという時、
観客に強い印象を与えるのに十分ではないことにリハーサルで彼は気付きました。
そして、この英雄がどのように立ち、駿馬の様に跳躍し、
いかに静かに剣を取るのか教えてくれたのです。
彼の繊細な指導が無かったら私のキャリアは今とは違うものになっていたでしょう。
彼に出会い、その短い人生の旅路の幾ばくかの時を共に歩んだことは、
感謝しつくせないほどの贈り物なのです。」
ピアニストのゲザ・アンダ曰く、
「最初、聴衆には『理解できないノイズ』として現れた、バルトークのピアノ協奏曲2番。
しかし、この曲が実際には非常にロマンチックな音楽であると私達は確信しました。
私はシューマンの作品を弾くときの様にピアノを弾き、
彼は『伴奏』という概念を超えてブラームスの交響曲の様に指揮しました。
このベルリン放送o.との録音でディスク大賞を受賞した直後に、
今度はウィーン・フィルとも演奏する事になったのです。
これは私の最も大切で美しい思い出の1つとして、いまも忘れ得ぬ素晴らしい体験でした。」
ヴァイオリニストのユーディ・メニューイン曰く、
「彼が楽譜を紐解いたとき、その音楽作品は情熱に満ちた小説へと変わりました。
危機と慈愛、喜びと苦痛が、連続した物語の中で繋ぎ合わされていくのです。
音楽においてドラマチックな小説を作り上げたので、
彼の人生において他の文学は必要なかったでしょう。
例えば、ドヴォルザークの「新世界」を彼が解説してくれたことがあります。
約束の地であるニューヨークの霧から立ち上がる尖塔、
移民たちの故郷への思い、そして苦難の旅路。
こういった心情を音楽で描くことが如何に重要であるのかを私は教わったのです。
彼が卓越したオペラ指揮者だったのも全く不思議ではありません。
フリッチャイの心が描く絵画の鮮やかさ、色彩と、奏でる音楽が一致したとき、
それは聴衆の心に直接突き刺さるのですから。
これらの思い出は、私の音楽人生で最も楽しかった瞬間の一つです。」
とあるジャズ・ミュージシャンを共演者が賞賛した言葉に、
「彼は素晴らしい音楽家であるだけじゃなく、音楽を『旅』に出来る人なのよ。」
といったものがある。
フリッチャイもまた、最高の音楽家の中でも一握りの人間だけが持つ
情景、心象風景を音楽で描き出すという特異な才能を、
その短い人生において眩いほどに輝かせた指揮者だった。
フリッチャイの在庫を見る
Eduard van Beinum(1900-1959)
【主な活動レーベル】
英DECCA
蘭PHILIPS
【経歴について】
オランダ東部の街アーネムにて生を受ける。
祖父は指揮者、父はコントラバシスト、兄はヴァイオリニストという音楽一家で育ち、
幼少期からヴァイオリンとピアノのレッスンを受ける。
兄のピアノ伴奏をし兄弟デュオでの活動もしていたが、
1918年にヴァイオリニストとして地元のアーネム管弦楽団に参加。
アムステルダム音楽院に進学すると指揮も並行して学び始め、
ヴァイオリン、ピアノ、指揮と三足の草鞋を履いて研鑽を高めた。
25歳には指揮者への道を歩むことを決意。
当初は矢張り地元のアーネム管弦楽団で活動していたが、
27歳の時にオランダ北部の「花の街」、ハールレムの交響楽団に音楽監督として招聘される。
ベルリオーズ、ドビュッシー、ラヴェルなどフランス作品を主軸に演奏し名声を高めると、
29歳にして遂にオランダ最高のオーケストラであるコンセルトヘボウ管弦楽団に客演。
首席指揮者メンゲルベルクと客演指揮者ピエール・モントゥーの推薦もあり、
2年後には空席だった第二指揮者に任命されて同楽団に籍を移す。
そして、このコンセルトヘボウとの出会いこそベイヌムにとって運命の転機だったと言える。
支配的かつ抑圧的で、濃厚な味付けをほどこす、
言わば前時代的な指揮者だったメンゲルベルクに対し、
楽団員と良く会話し、客観的視点で素材をそのまま活かすベイヌムは
目指す方向、志向が余りにも真逆だった。
ただし、これは当時の指揮者としてはベイヌムの方が異端で、
楽団員からの熱い信頼に比べ、聴衆からは「冷淡」な音だと捉えられてしまった。
情熱が全面に出たメンゲルベルクの分かりやすさを当時の聴衆は大いに支持しており、
また、これこそオランダが誇るコンセルトヘボウの音であると理解していたのだ。
この環境の中、ベイヌム自身にどういった葛藤が有ったのか今や知る由もないが、
1937年にオランダで2番目の実力を持つレジデンティ管弦楽団が
首席指揮者のオファーを出した際、
少なくともベイヌム自身は移籍に乗り気だったという。
そこに待ったをかけたのが、日頃から深い交流を持っていた楽団員たち。
最愛の指揮者ベイヌムを繋ぎ止めるために運営に働きかけ、
なんと翌1938年からは首席指揮者を二人置くという、
世にも珍しいスタイルを確立してしまった。
首席に就任した後は並行して欧州各地で客演指揮者としての活動を続けるベイヌムだったが、
当然のことながら地元への貢献も忘れてはいなかった。
オランダの地にブルックナーの交響曲を紹介したのはベイヌムだと言われているのだ。
メンゲルベルクによって確立されたマーラーと、
ベイヌムが伝えたブルックナーとは、
コンセルトヘボウの恒久的なレパートリーとして後世に残る事となる。
事態が動くのは第二次大戦が終わった1945年。
ナチスから招聘されベルリン・フィルを客演した事などが問題視され、
メンゲルベルクがオランダ音楽界から追放されてしまうのである。
結果として本来的な意味での首席指揮者の座にベイヌムは昇格した。
そこには既にメンゲルベルクの影は無く、
大手を振るって、気の知れたオランダ最高の楽団を指揮する舞台だけが残っていたのだ。
1945年から46年にかけては100回を超えるコンサートを行い、
マーラー、ドビュッシー、チャイコフスキー、メンデルスゾーンなど、
戦中に禁止された「退廃芸術」の作品を5年ぶりに聴衆に披露した。
そしてオランダ以外の欧州の音楽界もベイヌムを待ち望んでいた。
1947年のこと、7年も空白だったロンドン・フィル首席指揮者にベイヌムを招聘したのだ。
しかし、順風満帆に見えるベイヌムの身体には病魔が忍び寄ってきていた。
ベイヌムは、この頃から晩年まで心臓系の疾患に悩まされていたと言われている。
1949年までの2年をロンドン・フィルと過ごした後、体調不良を理由に離籍。
オランダ国内に専念した1950年のシーズンも満足な活動は出来なかった。
復調の兆しが見えだしたのは1954年を過ぎてのこと。
フィラデルフィア管弦楽団で米国デビューを果たすと、
同年の冬からはコンセルトヘボウ初の米国ツアーも行い新世界側での名声も獲得。
1956年にはロサンゼルス・フィルの音楽監督にも招聘、
アムステルダム大学から名誉博士号を授与、オランダ芸術評議会に選出など
オランダを代表する人物としての揺るがない地位を確立した。
だが、指揮者として頂点を極めつつあったベイヌムの最後は突然だった。
1959年4月13日、彼の心臓は突如として鼓動を止めたのだ。
四半世紀以上の歳月を共に過ごしたコンセルトヘボウ管弦楽団と、
ブラームスの交響曲第1番をリハーサルをしていた最中のことであった。
生前のベイヌムには一つの夢が有った。
それは世界中のミュージシャンが勉強会を通じて交流する国際的な出会いの場、
言うなれば「未来の音楽センター」を設立することである。
コンセルトヘボウ首席ハープ奏者のベルグハウトと共に、
50年代初頭から計画を推進していたのだ。
残念ながら生前に夢を叶える事、そして行く末を見守る事は叶わなかったが、
急逝の翌年、1960年11月16日に努力は実を結んだ。
現在に至るまでオランダおよび欧州音楽界への貢献を続ける、
エドゥアルト・ファン・ベイヌム財団が発足したのである。
死してなお、ベイヌムの温かい眼差しはオランダと欧州の音楽界を見守り続けている。
【演奏スタイル】
日本では前任のメンゲルベルク、後任のハイティンクの知名度の陰に隠れているが、
ベイヌムこそコンセルトヘボウの中興の祖であり、
またコンセルトヘボウの黄金期を作り、『らしさ』を引き出した最後の指揮者である。
メンゲルベルクの古典的、ロマン主義的な味付けに掌握されていたコンセルトヘボウは、
ベイヌムの手腕によって風味を残しつつも近代に通用するサウンドへと進化を遂げた。
しかし、彼が急逝し後任のハイティンクが就任すると現代趣味が先行する様になり、
或る意味で味付けの無い万能型にコンセルトヘボウは変遷していく。
ベルリン・フィルやウィーン・フィルの様な楽団固有の味わいを残しつつ、
古臭くない近代的な感覚も取り入れたのがベイヌムのサウンドだった。
耳をすませば、コンセルトヘボウの渋い音色から生み出される
暗調で厳しさの漂う張り詰めた空気感を根底に感じることだろう。
感情に任せた表現を避けて、正攻法で真面目に取り組んだ録音が多く、
あまり大袈裟なところは無いが、勿論ただ大人しいだけではない。
長期に渡り親しまれる本物=スタンダードを示していたのだ。
くすんだ空が広がる欧州の冬を描いた様な、日本の侘び寂びに通じる様な、
中庸の美というものを知っている人だった。
更にレーベルとしては英DECCAと蘭PHILIPSという、
二つの高音質レーベルで録音を残している。
虚心坦懐に聴けば、驚く様な名演を再発見できるのではと思う。
また、音楽性と人間性は切り分けて考えるべきだが、
コンセルトヘボウの楽団員の直訴により
二人の首席指揮者が生まれた話に代表される様に、
同時代のアクが強い音楽家に比せば、まるで聖人君子の様な人物だった。
2004年にベイヌムの伝記を出版したトリュス・デ・ルールはこう語っている。
「この伝記を書くにあたり、編集サイドは『聖人伝』の様な内容にしては
絶対に駄目だと私に警告しました。
ですから、私は本当に丹念に彼の足跡を追ったのです。
しかし、何も見付けることが出来ませんでした。
我々がファン・ベイヌムを知ろうとして見付けられるのは、肯定的な逸話だけなのです。」
ベイヌムの在庫を見る
Gerhard Bosse(1922-2012)/ Gewandhaus Quartet
【主な活動レーベル】
ETERNA
世界最古の市民オーケストラ「ゲヴァントハウス管弦楽団」の地元である
ライプツィヒ地区に在るヴルツェンという町にて生を受ける。
軍楽隊だった父オスカーからヴァイオリンの薫陶を受けると、
高校を卒業後はライプツィヒ音楽大学でワルター・ダヴィソンに師事。
在学中からゲヴァントハウス管弦楽団へ客演していたという。
(ソリストではなく楽団員としての参加と考えるのが自然だろう)
1943年からはドイツに併合されたオーストリアで結成された
「ブルックナー帝国管弦楽団」に入団。
このオケはドイツ放送協会が主体となり、ドイツ各地の放送オケから名手を選抜し、
更に有望な若手をオーディションして組み合わせるという鳴り物入りで作られた団体。
このドイツ中の若手音楽家が集ったオーディションを見事に突破すると、
カール・ベーム、シューリヒト、カラヤン、
クナッパーツブッシュなどの大物指揮者と共演を果たした。
特にフルトヴェングラーの指揮には深い感銘を受けた事を後年ボッセは語っている。
しかし、第二次大戦を敗戦で終えると『帝国』の名を冠す同団体は解散を余儀なくされ、
ボッセ自身も1945年の暮れにはドイツへ戻る事になる。
翌1946年からヴァイマルのフランツ・リスト音大で教鞭を取っていたが、
1951年には地元「ライプツィヒ放送交響楽団(MDR交響楽団)」から
コンサートマスターとして招聘される。
また、同時に母校ライプツィヒ音楽大学の教授にも就任した。
ボッセのライプツィヒへの帰還は、東ドイツの音楽史にとって大いなる幸いだった。
その傍らにはヴァイマル時代にボッセに入門し、
ライプツィヒへも師事を受けるためにボッセを追いかけた俊英、
後にETERNAレーベルで名録音を幾つも残す事になるカール・ズスケが付き従っていたのだ。
そして1955年、ボッセは生まれ故郷とも呼べるゲヴァントハウス管弦楽団に
首席コンサートマスターとして凱旋することになる。
ズスケのライプツィヒ音大卒業と同年だったのが意図的か偶然かは判らないが、
当然、師に追従して愛弟子ズスケもゲヴァントハウス管弦楽団に入団する。
当時のオーケストラにはコンマスである第一ヴァイオリニストが頭領となり
弦楽四重奏団を組むのが『責務』だった節があり、
伝統あるゲヴァントハウス管弦楽団にも「ゲヴァントハウス四重奏団」が存在した。
コンマスの使命としてボッセも楽団からメンバーを選抜し、
第二ヴァイオリンには当時二十歳を過ぎたばかりのズスケを起用。
以降、1962年のズスケの「ベルリン・シュターツカペレ」移籍まで、
ゲヴァントハウス四重奏団はLP期において充実の録音を数多く残した。
ズスケが去る1962年にはゲヴァントハウスの首席指揮者コンヴィチュニーの主導により、
ライプツィヒ・バッハ・フェストにて「ブランデンブルク協奏曲」を演奏。
この演奏体験はズスケが去ってしまって以降のボッセにとって刮目すべき点が有ったのか、
1963年にはゲヴァントハウス選抜メンバーによる小規模オーケストラ、
「ゲヴァントハウス・バッハ管弦楽団」を設立。
この小編成オケは結成の年にETERNAレーベル初となる
「ブランデンブルク協奏曲」全曲録音を果たすが、
この際にはズスケをベルリンから客演として呼び戻し
結果として後世に残る素晴らしい成果をあげている。
その後のボッセは1987年までゲヴァントハウスを務めあげ引退するが、
なんと最終的には日本に永住し、その後の人生を全うする事となる。
日本の若手音楽家を育成する目的で毎年夏に開催される
『霧島国際音楽祭』を1980年から鹿児島の地で創立した縁から、
通訳を務めていた菅野美智子氏と前妻の死後に再婚したのである。
ボッセに最後の時が訪れたのは2012年2月1日のこと。
大阪府高槻市の自宅で大腸癌の合併症により逝去。
享年は90歳だった。
ドイツのレコード史に於いての大きな過ちとして、
ボッセをソリストに擁立しての録音を行わなかった事が挙げられる。
本人がアンサンブル・プレイヤーとしての道を全うしたかった、
ズスケなどの後進に道を譲った...等々の憶測は立てられるが、
いずれにしても楽曲構成に於ける『ヴァイオリン・パートの独奏部分』しか、
この名手の手腕を満足に楽しめないのは余りに惜しい。
と言うのも、愛弟子ズスケとはスタイルが明らかに異なっているからだ。
ズスケを聴けばボッセの演奏も理解できるとは口が裂けても言えないことだろう。
オーディオ文化が盛んになっていく時代的なものも有るだろうが、
そもそも地元ライプツィヒ生え抜きのボッセと、
現在のチェコで生まれたズスケで気風が違うのも当たり前である。
ボッセの根幹にはバッハの時代から受け継がれたライプツィヒ・スタイルが根強い。
しかし、その峻厳たる表情の中にも、しなやかな歌心を感じるボッセの演奏は、
「ドイツ風」スタイルでありながら其処に安住しない心地良い渋色の音に満たされている。
どうしても「ズスケの師」という代名詞に捉われてしまうが、
ベートーヴェンの『Pf三重奏曲全集』などでボッセの描き出す世界に一度は触れて欲しい。
そこにはライプツィヒの伝統が脈々と息づいている。
ニーチェ曰く『いつまでも只の一弟子でいるのは、恩師に報いる道ではない』そうである。
ライプツィヒの伝統、正統を継承し教鞭を執れば偉大なる師であったボッセ。
師から大いに学び、後に師の亜流ではない自身のスタイルを確立したズスケ。
スタイルの異なる師弟二人の演奏の根底に流れる共通項を聴きとる時、
我々は同時に「音楽の神髄」を聴きとっているのではないだろうか。
ボッセの在庫を見る
Johann Karl Suske(1934-)/ Suske Quartet
【主な活動レーベル】
ETERNA
旧ライヒェンベルク(現チェコ領リベレツ)の生まれ。
戦中に紆余曲折の有った土地のため、チェコ出身とされる事も。
地元ライヒェンベルク管弦楽団でヴァイオリン奏者を務めていた父フランツから
幼少期よりヴァイオリンのレッスンを受けていた。
第二次大戦後はポツダム会談で決定された同地からのドイツ人追放令を受け、
1946年にドイツ領テューリンゲン州に移住。
1948年頃に同州ヴァイマルにあるフランツ・リスト音大に入学した。
この学び舎には、生涯に渡り影響を受ける事となる恩師、
ゲルハルト・ボッセとの出会いが待っていた。
1951年にボッセが「ライプツィヒ放送交響楽団(MDR交響楽団)」のコンサートマスター、
およびライプツィヒ音大の弦楽器科の主任教授に抜擢されると、
それに従ってライプツィヒに居住を移す。
また、この時にボッセが設立したボッセ四重奏団にも第二ヴァイオリンとして参加。
(残念ながらボッセ四重奏団名義でのレコード録音は残されていない)
1955年頃にズスケがライプツィヒ音大を卒業するのと時を同じくして、
ボッセがライプツィヒの「ゲヴァントハウス管弦楽団」のコンサート・マスターに就任する。
もちろんズスケも迷うことなく同楽団への入団を決めた。
転機が訪れるのは1962年のこと。
ゲヴァントハウス管弦楽団のカペルマイスター(楽長)だったコンヴィチュニーは、
ベルリン歌劇場付きオケ「ベルリン・シュターツカペレ」の楽長も1955年から兼任していた。
このコンヴィチュニーがズスケを同楽団のコンマスとして移籍させようとしたのだ。
移籍に際してボッセとどんなやり取りがあったかは不明だが、結果これを承諾する。
首都ベルリンに移住も決め、ヴァイオリン首席奏者として華々しくデビュー…の筈が、
なんと招聘したコンヴィチュニー本人が同年に心臓発作で急逝してしまう。
ただ、後任を務めたオトマール・スウィトナーとも良好な関係を築けた様で、
1964年にソリストとして初録音したハイドンのVn協奏曲を筆頭として、
10年以上の長きに渡り充実した録音群を残している。
そして1965年、遂に自分の名を冠した「ズスケ四重奏団」が設立される。
第一Vnであるコンマスが弦楽四重奏団を設立する事は伝統的な責務でもある。
オーケストラの公式団体としての弦楽四重奏団は、
リーダーが交代しても他のメンバーは在留する場合も少なくないが、
ズスケは全員を新メンバーとした。
コンマス就任が1962年だった事から考えると、
3年という月日をかけて自分の眼鏡に敵う人物を探していたのだろう。
その人選に狂いはなく、ベートーヴェンの弦楽四重奏曲全集が完結する、
1980年まで一人のメンバー交代も無く活動を続けた。
さて、ここからが複雑な話となる。
国内ではズスケ四重奏団の名で活動していたが、
外国向けには『ベルリン・シュターツカペレの四重奏団』として、
「ベルリン四重奏団」の名が使われているのである。
そして更に、1975年にズスケはゲヴァントハウス管弦楽団に出戻る。
師であるボッセが指揮者としての活動の多忙などのためコンマスの引退を決意、
後任には愛弟子のズスケしか考えられない、という意向だったと思われる。
残されたベルリン・シュターツカペレのコンマスにはバッツドルフが就任。
ここでも伝統に則りバッツドルフは新団体としてのベルリン四重奏団を創設する。
しかし、突然の交代だったためか第一ヴァイオリンのバッツドルフ以外は、
ズスケ四重奏団のメンバーが残るのだ。
リーダーだけが違うベルリン四重奏団がここに生まれるのだが、
なんと進行中だったベートーヴェンの弦楽四重奏曲全集の録音を完結させるため、
1980年までズスケ四重奏団としても並行して活動を続ける異常事態が生まれる。
ズスケ本人はゲヴァントハウスのコンマスとして、
「ゲヴァントハウス四重奏団」のリーダーの責務がある中での話なので
ベルリンとライプツィヒを行ったり来たりの生活を送ったことになる。
しかもETERNA録音の大半がドレスデンのルカ教会スタジオである。
この時期のズスケはドイツ南北間の大変な移動を毎度の様に行っていた事だろう。
また、ETERNAレーベルとしても録音計画を大いに考え直す羽目になる。
今となっては笑い話だが、当時のスタッフ達は大いに苦悩したことだろう。
ボッセとズスケの師弟愛が各所に迷惑と混乱を巻き起こしたのは想像に難くない。
究極はレコード番号725 130「メンデルスゾーン:弦楽八重奏曲」。
俗に言う「ダブル・カルテット」編成の曲だが、
ライプツィヒに出戻ったズスケがリーダーを務めるゲヴァントハウス四重奏団と、
バッツドルフ以外はズスケ四重奏団のメンバーが依然として残っている
ベルリン四重奏団の組み合わせで演奏しているのだ。
第3ヴァイオリン(四重奏団2組目の第1ヴァイオリン)として参加した、
バッツドルフの心情を慮ると何とも複雑な気持ちになってしまう。
1980年にベートーヴェン全集録音を終えると同時に、
ようやくズスケ四重奏団としての活動を正式に終了。
その後はゲヴァントハウスのコンマスとして、
もちろん同時にゲヴァントハウス四重奏団のリーダーとして、
冷戦終結=東西ドイツ併合まで幾つかの録音を残した。
ズスケの録音を聴くと分かる興味深い事実は、
師であるボッセとは音色やスタイルが大きく異なることである。
上等な柿渋染めの様な穏やかさと繊細さが特徴の師ボッセに対し、
深山の清流の様な澄み切った音色で楽曲を描き出すのがズスケである。
片やバッハ以来のライプツィヒの伝統の継承者である師と、
片や現在のチェコ出身で師のスタイルを更に進化させた弟子、といったところか。
いずれにせよ親子の様に長年連れ添った師弟と云えども、
奏でる音は飽くまで個人に拠るものである当然の事実を物語っている。
そして、愛弟子が自分とは違う手法で手に入れた成功を、
師ボッセが心から嬉しく思っていた事も容易に推察できる。
前述の通り、ベルリンから再度引き抜いてまで自分の後任を託したのだから。
最後に余談だが、ズスケの血を引く4人の子供のうち、
1人は作曲家となり、残る3人は全てゲヴァントハウス管弦楽団と関わりを持つそう。
特にコンラート・ズスケはアソシエイト・コンサートマスター、
副・第1ヴァイオリンとして2023年現在もゲヴァントハウスで演奏を続けている。
1948年ヴァイマルの地で偶然巡り会った二人のヴァイオリニストの絆が、
現代のライプツィヒの地にも大いなる福音をもたらしている。
人の運命とは、まこと数奇な物である。
ズスケの在庫を見る
Jean-Pierre Rampal(1922-2000)/ Quintette a Vent Francais
【主な活動レーベル】
仏国内のマイナーレーベルを含めた、
おおよそ想定されるであろう全レーベル
稀代のフルーティスト、ランパルは1922年マルセイユの地に産声を上げた。
父親ジョセフはパリで学んだ後に地元マルセイユ音楽院で教鞭を執るフルート奏者だったが、
両親は息子に音楽家よりも堅実な道を選ばせたかったらしく、
1940年の進学の際にはマルセイユ大学の医学部に進む事となる。
転機が訪れるのは1943年のこと。
第二次大戦においてマルセイユの地がナチスに占領されてしまい、
ランパルもパリの医学研究所に送られドイツ軍に奉仕することを余儀なくされる。
が、ここで偶然かつ運命的な事件が起きた。
到着してすぐ、パリ音楽院への入学試験が行われる事を知らされるのである。
この時、前任のアンリ・ラボーと現任のクロード・デルヴァンクール両院長は、
学生がドイツ軍によって徴発や占領される危険に対し授業を継続する方針を立て、
新しく学内オーケストラを設立するなどの対策を取り強制移住や強制労働を防いでいた。
軍属でも2週間の休暇を取って試験に参加できる事を知るとランパルも入学を決意、
ここで見事に合格し1944年からパリ音楽院で学ぶこととなる。
在学期間はパリが連合軍に解放されるまでの4~5か月程度だったというが、
この短い在学期間の中でも頭角を現した記録が今も残っている。
教授を務めていた作曲家ジョリヴェが卒業試験用に書き下ろした「リノスの歌」を吹き、
父ジョセフと親子二代に渡っての首席卒業を果たしているのだ。
卒業後の1946年からは本格的な音楽活動を開始する。
パスキエ・トリオとのモーツァルト「フルート四重奏曲/K.285」で初録音、
パリ音楽院のOBを集めた「フランス木管五重奏団」の立ち上げ、
パリ音楽院の同級だったロベール・ヴェイロン=ラクロワとの演奏会の立ち上げなど、
終戦後のフランスを音楽で盛り上げる大活躍を見せるのである。
また、1948年には『伝説の楽器』と運命的な出会いを果たす事となる。
フルート界で高名な職人ルイ・ロットが1869年に唯一作ったという純金製の楽器、
その名も『No.1375』である。
第二次大戦以前からルイ・ロットが唯一作った18金のフルートが存在するらしい…
そんな都市伝説がまことしやかに囁かれていたのだが、
偶然にもランパルは骨董品ディーラーによって溶かされる寸前だった所を見付け出したのだ。
購入に際し資金協力もしてくれた父ジョセフに楽器を送ると、
ジョセフは昼夜を惜しんで修復に取り組んだという。
この頃にはランパルが音楽の道を究める事について、両親が同意していた事実が窺える。
実は父ジョセフはパリ音楽院出身で、師であるモイーズから将来を嘱望されていたが、
第一次大戦で兄を亡くした過去から故郷で家族と共に過ごす道を選んでいたのだ。
この楽器のエピソード以外にも、ジョセフは晩年まで息子を支え続けながら、
地元マルセイユ音楽大学の教授として教育活動を続け、
マクサンス・ラリュー、アラン・マリオンなどの名フルーティストを育成した。
この父の献身と、80年の歳月を経ても失われたパーツが無かった奇跡もあり、
『No.1375』は完全復活し、ランパルの初期録音で我々の耳を楽しませてくれる。
伝説上のフルートを現代に甦らせた点でもランパル親子の功績は大きい。
しかし、余談だが、ランパルは、この伝説の楽器を、こともあろうに、
落として、壊している…。
偶然にも来日中の出来事でヤマハの技師が修復したが、
修理担当者は気が気で無かっただろう。
当時のエピソードは下記ページで確認出来る。
外部ページへ移動
1949年にはパリの超名門音楽ホール『サル・ガヴォー』にてリサイタルを開催。
ラクロワとのデュオで行われたこの演奏会は一大センセーションを巻き起こしたという。
フルートと鍵盤だけで構成された大規模なリサイタルなど、
世界中の誰も見たことが無かった時代である。
更に、プログラムには曰く付きのフルート曲として知られる、
プロコフィエフ「フルート・ソナタ Op.49」のフランス初演も含まれている。
難曲過ぎてヴァイオリン・ソナタ2番として改訂されていた曲が、パリで陽の目を見たのだ。
このデュオが定期的にラジオ放送を行うと評判は飛び火していき、
招きに応じてヨーロッパ各地を飛び回る事となる。
1950年にはLPレコードへの録音を開始。1970年までに20を超える国内外のレーベルへ録音。
1952年「フランス木管五重奏団」にラクロワ等が加わり、
「パリ・バロック・アンサンブル(Ensemble Baroque De Paris)」を結成。
1953年にはERATOレーベルが創設。ランパルはここに約100枚のディスクを録音する。
1954年リステンパルト×ザール室内楽団と活動開始。ここでも伝説的名盤を数多く残す。
ランパルの活躍は到底ここには書ききれない為、下記のページなどを見ていただきたい。
外部ページへ移動
途轍もない量の録音を残し『レコード史』に大いに貢献したランパルだが、
実は『フルート史』への貢献こそ、録音と比較にならない程に巨大な成果である。
古楽から現代曲に至るまで数多くのフルート作品を事実化した功績は、
まさに『偉業』と呼ぶに相応しい。
特に、バロック作品への尽きない興味は10代の頃から始まった嗜好だそう。
パリ、ベルリン、ウィーンなどヨーロッパ主要都市の図書館(古文書館)を回り、
音楽学者などの専門家たちと交流を深め、バロック作品への理解を深めていった。
タルティーニ、チマローザ、サンマルティーニ、ペルゴレージ、
ドヴィエンヌ、ルクレール、ルイエ、フリードリヒ大王など、
フルート界から「失われて」いた作品を見つけ出し現代に甦らせたのである。
もちろんこれらのバロック研究は室内楽分野でも実を結ぶ。
「フランス木管五重奏団」や「パリ・バロック・アンサンブル」は、
18世紀の室内楽を世界に知らしめる嚆矢、端緒となったグループだろう。
そして更にはドビュッシー、ラヴェル、ルーセル、ミヨーらのフランス近代作品から、
バーンスタイン、ペンデレツキなどの現代音楽、果てはジャズまでを演奏した。
もちろん中間地点にあたるロマン派の作品にも大いに手を付け、
およそフルートという楽器が演奏できるであろうレパートリーにおいて、
作品の成立した時代が断続しない様に気を付けていた。
或る批評家は「彼はアレキサンダー大王だ、もはや征服する新しい世界がない」と表現した。
この節操が無い様に見える縦横無尽の活躍には一家言ある方も多いだろうが、
ランパルは自伝の中で、フルート奏者「全体」のレパートリーを、
可能な限り拡大することが自身の義務なのだと語っている。
音楽家個人、或いは独りのフルーティストとしての承認欲求を満たそうとする姿勢は、
少なくとも残された発言からは見当たらない。
「節操が無い様に見える」という話では、
時代による音楽性の大きな変化もランパルの評価を難しくさせている一因だろう。
1950年代には抑制が掛かった少し暗調な表情でヴィブラートが綴れ織られていく繊細なもの。
それが1960年代には出自であるラテン系の明るい音色に徐々に移行していく。
1970年代ともなれば、このラテン的な音楽像は加速の一途を辿っていく印象を受ける。
明瞭な表情、表現の代償として、思索に満ちた初期録音に比べれば、
「深み」が欠けている様に聴こえてしまうのだ。
件の『No.1375』という楽器が貴重過ぎてヘヴィユーズが困難だった事や、
各国のフルート工房に求められ開発協力を行っていた事など、
楽器そのものの変遷自体が、音像が変化してしまった大きな原因の一つだろう。
一般的に、演奏家に使い込まれていない新作楽器からは深い音色は生まれてこない。
(ファンタジィやプラシーボの話ではなく、音響特性の変化の問題である)
しかし極東の一企業であるヤマハが『手工フルートの工房』として、
欧州を含めた世界的な名声を確立できたのはランパルの助力が有ればこそである。
いずれ、『フルート史』への貢献と『レコード史』への貢献を同時に果たすのは
神ならぬ一人の身体では至難だった、というところだろうか。
しかし、ランパルが、或いはランパルと父のジョセフが、
フルートという楽器に捧げた貢献は、あまりにも、あまりにも大きい。
20世紀中盤以降のフルート奏者は、須らく皆がランパルの恩恵に預かっている。
パリ14区、モンパルナス墓地の第三区画。
「Famille Rampal」と書かれた黒い墓碑。
人生を賭して家族を愛した父ジョセフ、そして最愛の母アンドレーと共に、
この偉大なるフルーティストは永遠の床に伏している。
ランパルの在庫を見る
Jacques-Louis Parrenin(1919-2010) / Quatuor Parrenin
【主な活動レーベル】
VÉGA
先に挙げているランパルと真逆で、
個人の情報が非常に少ないのがパルナンというヴァイオリニストである。
パルナンは1919年にチュニジア北部のフェリービル(現メンゼル・ブルギバ)に生まれる。
父のフランソワが海軍の軍医だったため、遠いアフリカの地での出生となったのだろう。
その後、フランスに移り南西部ロリアンの高校を経て、パリ音楽院を首席で卒業。
…この程度の情報しか得られないのだ。
当然ながら各国のウィキペディアにも記事が無い。
これは中国史でいえば個人の『列伝』が無いということ。
ちなみに、娘であるエマヌエルはフォーク・シンガーとなったが、
彼女にはしっかりと個人記事があるのにも関わらずである。
対して、パルナン四重奏団となると急に情報が増えるから不思議なもの。
パルナン四重奏団は1942年にパリ音楽院の教授ジョセフ・カルヴェ門下の四人で結成した。
師カルヴェはSP期にカルヴェ四重奏団という名団体を率いていたが、
戦争で活動がままならなくなり後進への指導に重心を移していた。
ランパルの項でも書いたが、当時のパリはドイツ占領下という苦難の時代である。
クロード・デルヴァンクール院長は合法非合法問わず手を尽くし、生徒を守った。
そしてパルナン達も二人の師の期待に応えるかの様に、
1944年にパリ音楽院の室内楽部門で首席を取り卒業した。
卒業後はルクセンブルク放送局などで演奏していたが、
その実力は誰しもが認めるところだったらしい。
ハイドン、モーツァルトの古典からラヴェル、ドビュッシーなどの定番曲も巧みだったが、
『新ウィーン楽派』と言われるシェーンベルク、ベルク、ウェーベルンの三人の作曲家、
新鋭たる彼等の作品を全て弾きこなせる団体など当時に於いては存在しなかったからである。
この強固なアンサンブルは卒業後に8年ほども続けたという共同生活で築き上げたものだろう。
若き卒業生を支えるために貢献したのは、またもデルヴァンクール院長だった。
共同生活の為の住居を用意し、心ゆくまでアンサンブルを鍛える環境を与えたのだ。
そして音楽史で言えば、時はまさに現代音楽の隆盛期。
戦争と共に40年代が終わり、新世代の訪れを予感させる空気の中をパルナン達は駆け抜けた。
同時代の作曲家であるクセナキス、ブーレーズ、ペンデレツキ、リゲティ等の依頼を受け、
150以上の作品を世界初演する偉業を果たす。
そして遂には1952年の『リエージュ国際弦楽四重奏コンクール』、
現在の『エリザベート王妃国際音楽コンクール』に連なる大会で優勝を勝ち取るまでに至る。
1954年からは同級だったピエール・ブーレーズが立ち上げた演奏会イベントである
『ドメーヌ・ミュジカル』にも参加し、パリが音楽の中心地になっていく流れに貢献した。
『ドメーヌ・ミュジカル』は本邦で『現代音楽の領域』と誤訳(意訳)されている事と、
「鳥のカタログ」初演など現代音楽の大家メシアンの名が目立つ事とで、
良くも悪くも時代の最先端を突っ走った先鋭イベントと誤解されがちだが、
実際にはバッハからモーツァルトの古典、ラヴェルやドビュッシーなどの地元作品は勿論、
モンテヴェルディやダウランド、マショー、デュファイなど、
20世紀には忘れ去られていた古楽作品たち、
その復刻にも一役買っていたのが実は『ドメーヌ・ミュジカル』だった。
戦中には『退廃音楽』と迫害までされた現代音楽が、
実は悠久の音楽史の歩みの中では地続きである事を民衆に知らしめ、
音楽家たちには再確認させる意図がブーレーズには有った。
この志はパルナン四重奏団にも大いに影響を与えた事だろう。
音楽の中心地パリで活躍するパルナン四重奏団の名声は世界的にも広まり、
1953年から米国、オーストラリア、南アメリカ、日本と各地でツアーを繰り広げ、
1960年にはソ連に招待された最初のフランス団体という栄誉を得る。
そして1961年のメキシコ音楽祭で記念すべき2000回目のコンサートを行うまでに至った。
さて、これだけの輝かしいキャリアを持つパルナン四重奏団だが、
意外なことに録音作品、つまりレコードを選ぶ観点では注意が必要となる。
1951年のラヴェル「弦楽四重奏曲」が恐らく録音デビューと思われ、
50年代~60年代前半までは歴史的な名録音などを含めて
まさにフランスを代表する団体としての風格を見せていたが、
時が流れた1970年前後からは全く違う団体の様になってしまう。
どちらにも溢れるほどの魅力が有る事には違いは無いのだが、
時代の変遷と素直に飲み込むには余りに表情、表現が変わり過ぎている感がある。
原因として推察されるのは、メンバーの交代が多い団体だった事実である。
第2ヴァイオリンが2回、チェロが1回、ヴィオラに至っては4回も変わっているのだ。
共に戦火をくぐり抜けた志ある同窓生が作り上げたという結成の経緯からすると、
余りにかけ離れている事実ではないだろうか。
その理由について断定できる様な資料は見付からなかったが、
『tragiques accidents / 悲惨な事故』が原因だったと記述する資料が有る。
この単語の選択が意味するものについて想像する事しか出来ないが、
単なる不和とは違う、運命的、かつ悲劇的な出来事が起きたであろうことは推察できる。
繰り返す様だが、60年代後半以降のパルナン四重奏団にも魅力は溢れている。
第2Vnを新任したジャック・ゲステムは賛辞の言葉の尽きない名ヴァイオリニストである。
ただ、その輝きは戦火をくぐり抜けながらコンセルヴァトワールで学んだ、
初代メンバーが持っていた輝きとは違う種類のものなのだ。
手前味噌になるが、初代メンバーによるパルナン四重奏団の至高の名演は、
希少品であるオリジナル盤の入荷を待たずとも弊社CD-Rで聴くことが出来る。
強烈な再生音と共に、情感の揺らぎ、音色の絶妙な変化が押し寄せてくる、
室内楽のレコード史にとって『至宝』と呼ぶに相応しい傑作中の傑作である。
弊社CD-R紹介ページへ。
この圧倒的なパワーは若さによる力任せな情熱に拠るものでは決してない。
冷静かつ大胆、奔放にして理知的、妖艶にして清涼という、
フランス人が持つ『矛盾を内包した音楽的感性』の凝縮である。
フランスという国家が、パリという街が、コンセルヴァトワールという学び舎が、
ベルリオーズが、フォーレが、ドビュッシーが、ラヴェルが培ってきた土壌に、
大輪の花を咲かし見事に結実したのが当録音なのである。
21世紀におけるプレイヤー諸氏の『テクニック』の向上は皮肉無しに目覚ましいものだが、
作品の深淵を体現する意味での技巧が、眼前に絵画を想起させるが如き生々しい情感が、
この次元に辿り着けている録音は幾つ存在するのだろうか。
一聴いただき、匹敵する録音を思い付けたならば、それは途轍もなく幸福な事である。
当盤を知った後は、他の演奏が全て色褪せて聴こえてしまう危険性が有るからだ。
まして、オリジナル盤で聴いた日には、である。
貴殿のオーディオ・ライフに、幸多からんことを...。
【補遺】
上記した第2Vnを新任したジャック・ゲステムについても、
弊社でVn小品集をCD化しているので是非ご確認いただきたい。
各方面から名盤の誉れが高い、まさに珠玉の作品集となっている。
eterna-trading.jp/products/detail/34881
eterna-trading.jp/products/detail/34882
eterna-trading.jp/products/detail/34883
パルナンの在庫を見る
Willibald "Willi" Karl Boskovsky(1909-1991)/ Wiener Oktett
【主な活動レーベル】
Les Discophiles Français
DECCCA
ボスコフスキーは戦前当時の音楽の都ウィーンに生まれ、
母の指導で5歳からヴァイオリンを始めると9歳にしてウィーン音楽アカデミーに入学した。
在学当時から地元の「ウィーン国立歌劇場」でソリストとして客演していたが、
23歳となる1932年からは正式に「ウィーン国立歌劇場o.」に入団する。
翌年からは同歌劇場オケの選抜メンバーにより結成された、
「ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団」にも昇格入団。
この時は第2ヴァイオリン末席という下っ端も下っ端でのスタートだったという。
しかし、他の名匠たちの御多分に漏れず、戦争が状況を変えてゆく。
1938年3月、ナチスのオーストリア併合によりウィーン・フィルは解散の危機を迎える。
この時はフルトヴェングラーの尽力も有り解散は免れたが、
ナチス管理下に置かれる事を余儀なくされ、ユダヤ系団員の排斥が始まってしまう。
マーラーの義弟だった首席コンサートマスターのアルノルト・ロゼーを筆頭に
ヴァイオリニスト13人、その内コンサートマスター3人が追放される異常事態である。
当然ながら他パートのユダヤ系の演奏者たちも追放、或いは強制収容の憂き目に遭う中、
空席を埋める様に1939年にボスコフスキーはコンサートマスターに昇格した。
実はウィーン・フィルは団員にナチ党員が多かった経緯がある。
併合以前で25%、終戦までに最大で半数近くも居たとされ、
ベルリン・フィルの20%という数字に比べて歴然の差である。
これにはヒトラーがオーストリア出身だったことも関係しているのかも知れない。
いずれにせよ、戦争がウィーン・フィルに残した爪痕は深かった。
ナチスの傀儡オーケストラと見做された非業と言うべきか、
連合軍の空襲により本拠地であるウィーン歌劇場は焼け落ち、
ナチ党の籍を持っていた団員の多くが逃亡、あるいは追放された。
戦中から終戦直後にかけてはウィーン・フィルの暗黒時代と言って間違いないだろう。
ただ、そんな暗黒時代にも幾らかの明るいニュースは有った。
1942年にはオーケストラ創立100周年を記念し、
ウィーン歌劇場と、ザッハトルテで著名なホテル・ザッハーが並ぶ
アウグスティーナ通りの一部が「フィルハーモニカ通り」と改名された事がまず一つ。
そして何より、ボスコフスキーがコンマスに昇格した1939年に、
記念すべき第一回「ニュー・イヤー・コンサート」が開催されたのだ。
※この時は1940年の新年ではなく1939年の大晦日に開催したので、
1941年元旦に開催した2回目を初回とする意見もある。
ご承知の通り世界でもっとも著名であり、
もちろんウィーン・フィルにとっても最重要となるコンサートだが、
意外にもその歴史は100年にも満たない。
そして、このニュー・イヤー・コンサートこそが、
ボスコフスキーをウィーン・フィルの象徴に押し上げたのである。
多少横道に逸れながらの話となるが、その経緯を書いていきたい。
戦後のウィーン・フィルは戦争の爪痕を残しながらも、
世界的な指揮者を次々と客演指揮者に招聘し、徐々に復活の道を歩んでいった。
そもそもウィーン・フィルは1933年以降『首席指揮者』という存在を置かないという、
オケの比重が非常に強い世界的に見ても特殊なシステムで運営されていた。
しかし同時に、フルトヴェングラー、カール・ベーム、クレメンス・クラウスなど
重要なイベントでは絶対に招聘される『実質的な首席指揮者』が楽団を牽引していたのだ。
その中でもニュー・イヤー・コンサートは、
特別な事情を除いて発起人かつウィーン出身のクレメンス・クラウスが音頭を取っていた。
そのクラウスが様々な軋轢からの心労が祟ったのか1955年に急逝してしまう事で事態が動く。
ウィーンを代表するシュトラウス一家の曲をウィーンっ子達が演奏するのが、
ニュー・イヤー・コンサートのアイデンティティだったが、そこに大いなる問題が有った。
指揮者に於いて、ウィーン出身で世界的地位を誇る存在が居なかったのだ。
逝去したクラウスを除けばエーリヒ・クライバーしかビッグネームが居らず、
かつクライバーはドイツ的、かつ進歩的なスタイルを志向していた指揮者である。
伝統のシュトラウス作品でウィーンっ子が心弾ませ踊る様な指揮は望むべくもなかった。
そこで白羽の矢が立ったのが、順当に出世を重ね、
1949年から首席コンサートマスターに就いていたボスコフスキーだった。
そして、この起用は類を見ない程の大成功を収める事となる。
ヴァイオリニストが演奏しながら同時に指揮を振るうという、
『Stehgeiger(シュテーガイガー)』様式が時代を超えて復活するのである。
実はこの「弾き振り」こそ、家元ヨハン・シュトラウスをして、
19世紀当時の人々を魅了した大きな要因だった。
そして「写真」という技術が19世紀初頭に生まれた僥倖も大きい。
シュトラウス本人が指揮棒ではなく楽器を持ち演奏している姿を実際に視認し、
団員達も懸念の余儀なくボスコフスキーに全権を委ねる事が出来たのだ。
この世代交代を遂げた第二期ニュー・イヤー・コンサートは、
ウィーンっ子の諸手を上げての歓迎と熱狂は当然のこと、時代も大いに味方した。
1959年からは『ユーロヴィジョン』=『欧州放送連合』の電波に乗って、
欧州、そして世界中にニュー・イヤー・コンサートがテレビ中継される。
当時の恐らくほぼ全ての人が初めて目の当たりにしたであろう、
『Stehgeiger』スタイルでシュトラウス一族の華麗なる舞踊曲を
縦横無尽に弾きこなすボスコフスキーに世界中が熱狂。
シュトラウス作品とウィーン・フィルの名声を圧倒的に高めたと同時に、
音楽家個人としてのボスコフスキーもウィーンの伝統を背負って立つ名手として、
欧州中のオーケストラに客演依頼を受ける事となる。
そしてまた、音楽家ボスコフスキーを悩ませたのも
年月を経るごとに巨大になっていくニュー・イヤー・コンサートだった。
演奏曲目を事前にスタジオ録音するという方法で販売されるレコード、
悪ふざけと思えるほどに過剰になっていく舞台演出、
そして世界中を巻き込んで莫大な額となった放映権料…。
世界の潮流と同じく、ウィーン・フィルも商業の波に呑まれていったのである。
この「国際化」の流れに次第に疲弊していったボスコフスキーは
1966年に設立された『ウィーン・ヨハン・シュトラウス管弦楽団』に重心を移し始め、
1969年に創設メンバーのエドゥアルト・シュトラウス2世が早逝すると首席指揮者に就任。
そして自身が体調を崩した1979年以降のニュー・イヤー・コンサートは、
ウィーン・フィルを振るに相応しい程度の実力と国際的名声が有る、
スター指揮者を客演として、あるいはタレントとして呼ぶ形に変遷させた。
もはや自分の手の届く範囲を遥かに超える怪物コンテンツとなった興行から、
成熟した音楽家へと老練したボスコフスキーは距離を取ったのだ。
ここまでが共に人生を歩んだウィーン・フィルに於けるボスコフスキーの足跡である。
ここからはボスコフスキーが遺したレコード文化への貢献の側面を御紹介したい。
在りし日のクライバーをして
「この楽団には幾つの弦楽四重奏団が在席しているんだ?」と言わしめた、
充実の弦楽器陣を誇るウィーン・フィル内にボスコフスキーも四重奏団を持っていた。
こちらは弟で首席クラリネット奏者だったアルフレッド率いる木管チームと合流し、
DECCAレーベルに充実の室内楽コレクションをもたらした
『ウィーン八重奏団』として結実する。
また、先輩コンマスであったバリリが肘を壊し『バリリ四重奏団』が立ち行かなくなると、
後を引き継ぎ『ウィーン・フィル四重奏団』として楽団を象徴する団体として再生させる。
こちらもDECCAレーベルに四重奏曲や五重奏曲においての重要曲で幾つもの名録音を残した。
そして最後に、言わずもがなの歴史的名録音の話となる。
現代に於いても燦然と輝く、Les Discophiles Françaisレーベルで行った、
リリー・クラウスと組んでのモーツァルト:Vnソナタの全集録音。
そしてチェリストのニコラウス・ヒューブナーが加わるピアノ三重奏曲の全集録音である。
モーツァルト生誕200年を祝って行われたこの録音は、
「20世紀最大のモーツァルトの理解者」と名高いリリー・クラウス、
後に異次元の高音質録音に取り組む若き日のアンドレ・シャルラン(パリ録音に参加)、
そして当時の世界最高峰であったPathé社のプレスという布陣で行われた。
結果、もはやLes Discophiles Françaisというレーベルを超え、
新たな「音楽の都」がパリである事を欧州中に知らしめる、
古今東西に比肩するものの無い究極の録音となった。
このDF録音に関して瑕疵が有るとすれば、唯一つである。
「盤質の良いレコードが殆ど存在しない」という、この一点。
モーツァルトという傑物が遺した偉大なる歴史に全力で傾注し、
その名に恥じぬ伝説的な録音を残すという成功を収め、
しかして完成したレコードの扱いは粗雑という尋常ならざるフランス文化…。
本邦の我々が理解できる日は、遥か、遥か遠い。
ボスコフスキーの在庫を見る
【 2023/6/24 更新 】